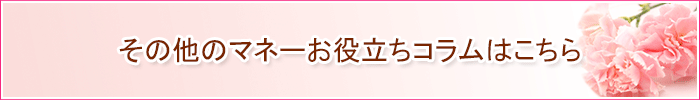自動車の維持費(ランニングコスト)ってどれくらい?平均費用や節約方法も紹介

自動車を購入すると維持費はどのくらい必要?
自動車を購入すると、購入時の初期費用(イニシャルコスト)はもちろんのこと、その後もお金がかかります。車は買えば終わりではなく、車に乗ったり維持するのに必要な「維持費」と言われる、継続的に発生する様々な出費(ランニングコスト)があります。
車の維持費は日々消費するガソリン代から税金、車検代まで様々で、中には車種によって金額が変動するものもあります。車の維持費は思いのほか家計を圧迫するため、維持費の安さで購入する車を検討する人もいるほどです。
この記事では、車にかかる維持費をはじめ、車種別の維持費の平均や節約方法について解説します。
乗用車には種類がある
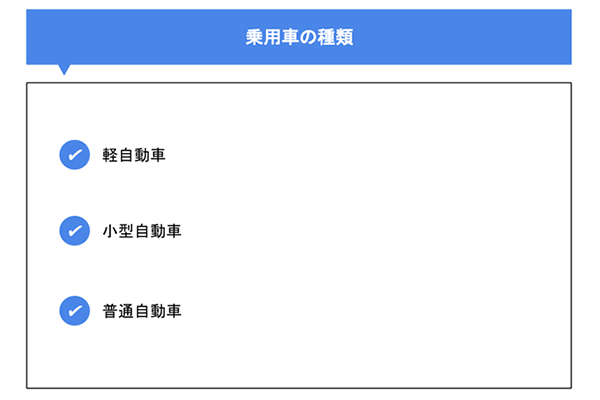
道路運送車両法では、自動車は「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」「大型特殊自動車」「小型特殊自動車(農耕作業用、荷役運搬・土木建設作業用)」の5種類に分類されます。その中で乗用車に該当するのは、普通自動車の「乗用車」、小型自動車の「小型乗用車」、軽自動車の「軽乗用車」の3つです。
車種によってそれぞれメリットとデメリットがあります。この項目ではまず、それぞれの乗用車の特徴を見ていきます。
軽自動車
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
軽自動車は乗用車の中で一番小型の車です。規格の制限で、全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0m以下、エンジンの排気量が660cc以下の車が該当します。
普通自動車や小型自動車の乗用車と比べ、車両がコンパクトなので、小回りが利き運転しやすいのが特長です。燃費も良く、維持費や高速料金も安いので経済的です。再販価値も高く、将来的に車を手放す予定がある場合にもおススメです。
定員は4名(または2名)なので、少人数や近距離での使用が多いのであれば便利ですが、5人以上は乗車できないのがデメリットです。ほかにも、長距離運転には向かず、車体が軽く衝撃にも弱いため、外的影響を受けやすいなど安全面でも懸念点があります。
小型自動車
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
軽自動車より大きく、普通自動車より小さいサイズで、一般的に「5ナンバー」「コンパクトカー」と呼ばれている乗用車です。車の規格は全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下、エンジンの排気量が660ccより大きく2,000cc以下のものが該当します。
小型自動車(コンパクトカー)の一番のメリットはコストパフォーマンスが良いところです。小回りが利き燃費が良いなど軽自動車のメリットを備えながら、一部の車を除いて5人乗りができ、安全性も高いことから、軽自動車のデメリットも補える万能タイプの車と言えます。
デメリットとしては、普通自動車と比べるとパワー不足で、長距離運転にはあまり向かないこと、高速などの有料道路では普通自動車の料金となり、軽自動車よりも高くなることが挙げられます。また、コスパが良い分、車内の内装等が見劣りするという意見もあります。
普通自動車
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
乗用車の中では一番大きく、一般的に「3ナンバー」と呼ばれている車です。小型自動車よりも大きい車が該当し、車の規格では全長4.7m以上、全幅1.7m以上、全高2.0m以上、エンジンの排気量が2,000ccを超えるものを指します。
普通自動車は5人以上の乗車が可能で、コンパクトカー以上に荷物を載せるスペースに余裕があります。運転のしやすさは軽自動車に劣りますが、運転中に疲れにくく、乗り心地、車内の静粛性など快適な環境で運転できるのがメリットです。ただし、車の維持費や燃費、高速料金など金銭面での負担は乗用車の中で一番大きくなります。
自動車の維持費(ランニングコスト)には何がある?

自動車の維持費は主に、「税金」「保険料」「メンテナンス費」「走行に必要な費用」の4つに分けられます。ここでは、それぞれの維持費の内訳について細かく見ていきます。
1. 自動車の維持費:税金
| 自動車税・軽自動車税 |
|
|---|---|
| 自動車重量税 |
|
車を所有すると、「自動車税(種別割)」や「自動車重量税」といった税金がかかります。
「自動車税(種別割)」は、毎年4月1日時点で車を所有していると発生する税金です。車種や排気量、用途、所有年数により納税額は異なります。普通自動車・小型自動車の場合は納付先が都道府県となり、軽自動車の場合は「軽自動車税(種別割)」という名称で市区町村へ納付します。
「自動車重量税」は自動車の重さで決まる税金で、自家用車の新規登録時と車検のタイミングで有効期間分をまとめて支払います。軽自動車の場合は車両の重さに関わらず定額です。13年以上、18年以上の経過のタイミングで税額が上がります。
また、2019年10月1日からは新たな税制度が適用されることになりました。2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用車は自動車税(種別割)の税率が引き下げられたり(※軽自動車税の税額は変更なし)、エコカー減税・環境性能割・グリーン化特例などの税額軽減措置を受けることができます。
2. 自動車の維持費:保険料
| 自賠責保険料 |
|
|---|---|
| 任意保険料 |
|
自動車を購入したら、自動車保険への加入が必要となります。自動車保険は自動車による事故や損害が発生した場合に、保険会社が保険金等によって損害を補償する保険のことです。自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」があります。
「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」は法律により車の所有者すべてに加入が義務付けられている保険で、他人への慰謝料や治療費などの損害に対しては補償されますが、自分の怪我や他人の自動車に対しては補償されません。自賠責保険が必要最低限の補償内容のため、多くの人は同時に「任意保険」にも加入し、自賠責保険では補えない損害をカバーします。任意保険の場合は保険内容により、保険料は異なります。
3. 自動車の維持費:メンテナンス費用
| 車検費用 |
|
|---|---|
| 修理代 |
|
| 消耗品の交換費用 |
|
自動車の維持費にはメンテナンスにかかる費用も含まれます。内訳は主に「車検費用」「修理代」「消耗品の交換にかかる費用」の3つで、中でも「車検」は自動車の維持費の中でも大きな出費の1つです。車検は「道路運送車両法」によって義務付けられた法廷検査のため、新車購入から3年後、その後は2年ごとに定期点検をする必要があります。費用は車種や車の状態、車検を行う場所によっても変わります。
そのほか、車が故障したときの修理代や、タイヤ、オイルなど消耗品の交換時にも都度お金がかかります。修理が続くと出費も多くなるので注意しましょう。
4. 自動車の維持費:走行に必要な費用
| ガソリン代 |
|
|---|---|
| 駐車場代 |
|
| 高速料金 |
|
日常的な出費となるのが、ガソリン代や各種有料道路の通行に必要な費用と、月々の駐車場代で、自動車の維持費の中でも大きな出費となっています。ガソリン代は車種や乗る頻度、走行距離だけでなく、ガソリンの相場によっても変動します。また、駐車場代は場所や地域によって大きく変わるなど、走行に必要な費用には個人差があるため、毎月チェックして支出を把握しておきたいところです。
自動車年間維持費の目安
| 項目 | 軽自動車 | コンパクトカー (普通車 1.5L) |
Lクラスミニバン (普通車 2.5L) |
|---|---|---|---|
| 自動車税 | 10,800円 | 30,500円 | 43,500円 |
| 自動車重量税 | 12,300円 | 16,400円 | 16,400円 |
| 自賠責保険料 | 12,422円 | 12,806円 | 12,806円 |
| 任意保険料 | 80,000円 | 85,000円 | 90,000円 |
| 車検代 | 25,019円 | 25,343円 | 25,470円 |
| メンテナンス費用 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| ガソリン代 | 81,152円 | 101,344円 | 135,203円 |
| 駐車場代 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 |
| 合計 | 380,693円 | 433,393円 | 487,379円 |
| 月平均 | 31,724円 | 36,116円 | 40,615円 |
- 上記の自動車税は2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた乗用車の場合
- ガソリン代は2020年5月27日時点のレギュラーガソリンの店頭価格(全国平均)126円から算出
- 車検代は東京都大手カー用品店の車検料金の平均値から算出
ここでは、自動車の維持費の目安を車種別に見ていきます。上記の表は、軽自動車、小型自動車(コンパクトカー)、普通自動車の3つを例に、それぞれ年間の維持費を概算したものです。軽自動車、小型自動車、普通自動車の順に維持費は高くなり、軽自動車と普通自動車では月平均で約1万円、年間では約12万円の差が出ることが分かります。
また、駐車場代以外は軽自動車の方が低額ですんでいることから、維持費だけで考えるなら、軽自動車を選ぶ方がおトクだという見方ができます。ただし、5人家族の場合は軽自動車だと全員で乗車ができないので、維持費で選ぶならコンパクトカーという選択になります。
車の維持費を節約する方法
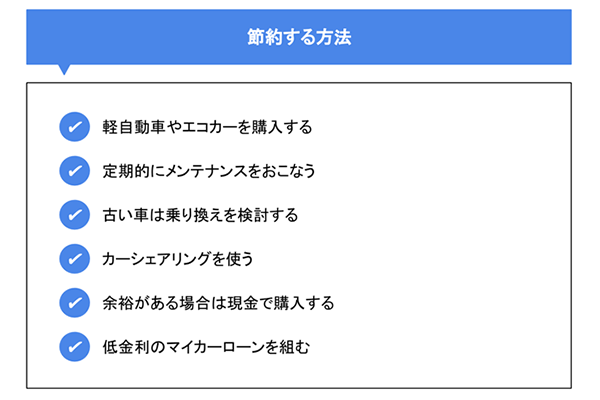
車の維持費は支払う頻度や時期がそれぞれ異なるため、普段はどのくらいの出費なのか気づきにくいものです。しかし、年間を通して見ることで、かなりの金額を支払っていることが分かります。ここでは、車の維持費を節約する方法について解説していきます。
軽自動車やエコカーを購入する
燃費や車検代、保険料などを考えると、前述のとおり、普通自動車よりも軽自動車の方が全体的に維持費が安いため、軽自動車を所有することで維持費を軽減するのは1つの方法です。
また、普通自動車や小型自動車(コンパクトカー)の場合でも「エコカー減税」の対象となる車を選ぶことで、自動車重量税の減免措置が受けられ、節税できます。エコカー減税による自動車重量税(重量税)の適用期間は2021年4月30日までです。
定期的にメンテナンスを行う
車は修理費にもお金がかかります。大きな故障による修理など、突発的な出費を抑えるためには、定期的にメンテナンスを行うことが大切です。まずは洗車と同時に車の状態も都度チェックするようにしましょう。日々のメンテナンスは大きな故障の防止と安全につながるだけでなく、結果、車検費が安くなり節約できる可能性もあります。
ワイパーやタイヤ、エアコンフィルター、ウィンドウォッシャー、バッテリー、エンジンオイルなど、定期的に交換が必要な部品のチェックも忘れないようにしましょう。
古い車は乗り換えを検討する
古い車は燃費が悪くなり、それだけでもガソリン代がかさみます。また、環境性能に優れたエコカーに対する減税制度ができた一方で、燃費が悪く環境に配慮されない古い車には自動車税が重課されるので、ますます維持費が高くなります。新規登録から13年(ハイブリッド車を除く/ディーゼル車は11年)を越えると自動車税は約15%の重課となり、軽自動車税も約20%の重課となります。自動車税は毎年支払う義務があるので、古い車に乗っているだけで維持費は増額してしまいます。13年が経過する前に車の買い替えも検討しましょう。
カーシェアリングを使う
自家用車を購入したものの、乗る機会が少なく駐車場代などがかさむ場合は、思い切って車を手放すことも1つの選択肢です。最近はカーシェアリングなど必要なときだけ車を利用することができる便利なサービスもあるので検討してみましょう。また、車検やメンテナンスなどの料金込みのカーリースを契約することでも、車の維持費は節約できます。
余裕がある場合は現金で購入する
ガソリン代などの走行費や駐車場代などは毎月発生します。車の購入時にローンを組んでいる場合、ローン返済も重なって一気に家計への負担が大きくなってしまいます。毎月の支出と家計への負担を減らすには、現金で車を購入することです。現金での一括購入が難しい場合でも、一部を現金で支払うことで、毎月の負担を減らすことが可能です。
低金利のマイカーローンを組む
月々の出費を考えると、車は現金での購入が理想ですが、マイカー購入時にはローンを組むのが一般的です。ローンを組む場合は少しでも金利の安い金融機関を選び、返済額を少なくしましょう。マイカーローンには銀行など金融機関で契約するものと、ディーラーなど自動車販売店で契約するものがあり、金利や手数料の安さで選ぶなら銀行など金融機関のマイカーローンがおススメです。
常陽マイカーローン「JOYO車」
常陽銀行のマイカーローンは、一度も来店せずにスマートフォンやパソコンでご契約可能です。ローンを申し込んでから車を選ぶことができ、中古車の購入にも利用できます。繰上返済手数料や保証料も無料となっています。
「インターネット仮審査」では、常陽銀行に口座がなくても申し込みができ、最短当日中に審査結果が分かります。
常陽マイカーローンについてはこちら
自動車購入は維持費を含めたトータルコストを算出して検討!

車両費などの初期費用だけでなく、自動車は継続して様々な維持費がかかります。維持費の総額は年間で見ると思いのほか高額のため、家計の状況によっては維持費の安さも車選びのポイントの1つとなります。
これから車を購入するのであれば、車両費だけでなく、車の維持費も含めたトータルコストを算出して検討するのが賢い選び方です。利用目的やライフスタイルに合い、経済的にも負担にならない車を選びましょう。
(2025年6月25日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以 上