
創業時からブレない
「お客さまの声を聞く」姿勢
ジョイフル本田が向き合う「地域課題」とは何ですか?
平山氏 : 少子高齢化が地域に与える影響については重く受けとめています。生産人口の縮小により、日本の多くの地域で厳しい状況が続いていくでしょう。これはリアル店舗を展開する当社の事業の継続にも大きく関わる問題だと捉えています。
一方、まだやれることがあるとも感じています。大切なのは自治体だけではなく地域の企業も一緒になってアイデアを出し、協力し合うこと。近年そうした話し合いの機会を常陽銀行さんが中心となって設けてくださっていて、非常にありがたく感じています。

ジョイフル本田が地域課題の解決に積極的なのはなぜですか?
平山氏 : 何よりもまず「お客さまのために何ができるか?」を考える。それがジョイフル本田が誕生からずっと大切にしてきたことだからです。話は創業時まで遡りますが、当社は創業者がアメリカの店舗に着想を得て、当時の日本では珍しかった材木や金物、工具などがワンストップで揃う、現在のホームセンターの原型となる店をつくったことにはじまります。
そして地域で選ばれ続ける、一番の店を目指す上で徹底していたのが「お客さまの声を聞く」ことでした。一つでも要望があった商品は必ず仕入れる。セット商品でも、一つだけほしいと言われたら袋を開けてお売りする。そうしたことをブレずに続けたことで、少しずつ信頼を獲得してきたのです。もちろんそれに合わせて商品の取扱量は膨大になり、売り場面積も拡大していきました。当社が現在のような超大型店となったのは、お客さまの声に応えてきた結果なのです。

私も入社してずっと、創業者や先輩方から「まずはお客さまが喜ぶことを考えなさい。効率や利益はその先にある」と言われ続けました。私たちにとって地域のお客さまのお困りごと、課題に目を向けることは、ごく自然なことなのです。

まちの起点となった店として、支えていく責任
地域の未来に向けたジョイフル本田の具体的な取り組みを教えてください。
平山氏 : 日々地域のお客さまの声に応え続けることはもちろんですが、とくに新たな店舗を出店をする際は「店舗を起点としたまちづくり」の視点を大切にしています。なかでも私たちにとって大きな挑戦となったのが、1998年のニューポートひたちなか店の出店です。
商業施設がほぼない工場地帯に、約3万坪の巨大な店舗をつくり、新たなにぎわいを生み出す。ともすると無謀にも思える計画ですが、創業者の頭の中には確かなまちづくりの絵が見えていたようです。ニューポートひたちなか店の出店後は、敷地内に当社初となる複合ショッピングモール「ファッションクルーズ」をオープン。さらに近くの海の景色を望む観光用ヘリコプターや船なども運行し、楽しさや驚きをお届けする多角的な施策を実施しました。その結果、近隣にTSUTAYAさん、ケーズデンキさん、ヤマダデンキさんなどが次々とオープンし、ひたちなか市の景色は大きく変わっていきました。

ひたちなか市は、その後の東日本大震災で大きな被害を受けた地域でもあります。そのようななかで、ニューポートひたちなか店はなんと翌日から営業を再開されました。当時、平山社長は店長を務められていましたが、どのような想いで現場の対応をされていたのでしょうか?
平山氏 : 思い出すのも辛いですが、震災直後は地域のほとんどの店が営業しておらず、生活に必要なものを手に入れることができずに困っている方がたくさんいらっしゃいました。だからこそ、できることをしたい。当時はその一心でしたね。
とはいえ震災の翌日は、うちの店舗も壁や天井が崩れかけ、とても通常の営業ができる状態ではありませんでした。それでも営業することを決めたのは、早朝から「お店、開けられますか?」と来られていたお客さまがいたためです。最初は数人ほどだったため、外で注文を聞いて私たちが店舗に入り商品を手渡していたのですが、気づくと駐車場には長蛇の列ができていました。

どこかで区切りをつけなければ…と思ってはいましたが、断れませんでした。なぜなら目の前に困っている方々がいるんですから。私たちはその後も安全を確保しつつ、できる範囲でお客さまに商品を届け続けました。非常に厳しい状況でしたが、うれしかったのは自宅が崩れたスタッフ以外全員が集まり協力してくれたことです。その後も福島から避難してきた方々の対応なども行い、お客さまからは「店が開いていてくれて助かった」という声をたくさんいただきました。
こうした非常事態に対応できたのは、これまでにも災害時にジョイフル本田が自治体や警察と連携し、その時に必要なものを迅速に取り揃えてご提供する積み重ねがあったからこそ。ひたちなか市は店舗を起点としたまちづくりを目指した地域でしたが、東日本大震災はほんとうの意味で地域に根ざす店舗になるには、大きな責任と覚悟が求められることを実感した出来事だったと思います。

地域課題の解決の鍵は、
「ステークホルダーとの対話」
地域のより良い未来をつくるために、ジョイフル本田が大切にしていることは何ですか?
平山氏 : 地域が抱える課題は複雑だからこそ、関係各所の協力なしに解決することは難しいと感じています。だからこそ私たちが重視しているのは、あらゆるステークホルダーと密につながることです。株主、お客さま、取引先、自治体、そしてもちろん従業員など、当社を支えてくださるすべての方々との「質の高い対話」を大切にしたいと考えています。

「ステークホルダーとの質の高い対話」に向けた取り組みの一つとして、2024年には社内外に企業的価値を発信する「統合報告書」を発表されていますね。常陽銀行も企画段階から制作の支援をさせていただきました。
平山氏 : 恥ずかしながら当社は対外的な発信が苦手で、統合報告書の発表は長年抱えていた宿題でした。とくに統合報告書は単なる財務情報だけでなく、ブランド価値といった非財務情報についての発信が求められます。当社の事業の考え方は創業からの歴史なしには語ることができず、どうまとめるか悩ましいところだったのですが、常陽銀行さんは私たちの声を丁寧にヒアリングし、プロの視点でメッセージをシンプルに伝えるためのサポートをしてくださいました。その理解の深さは、もはや私よりも当社について詳しいのではないかと感じるほどです。
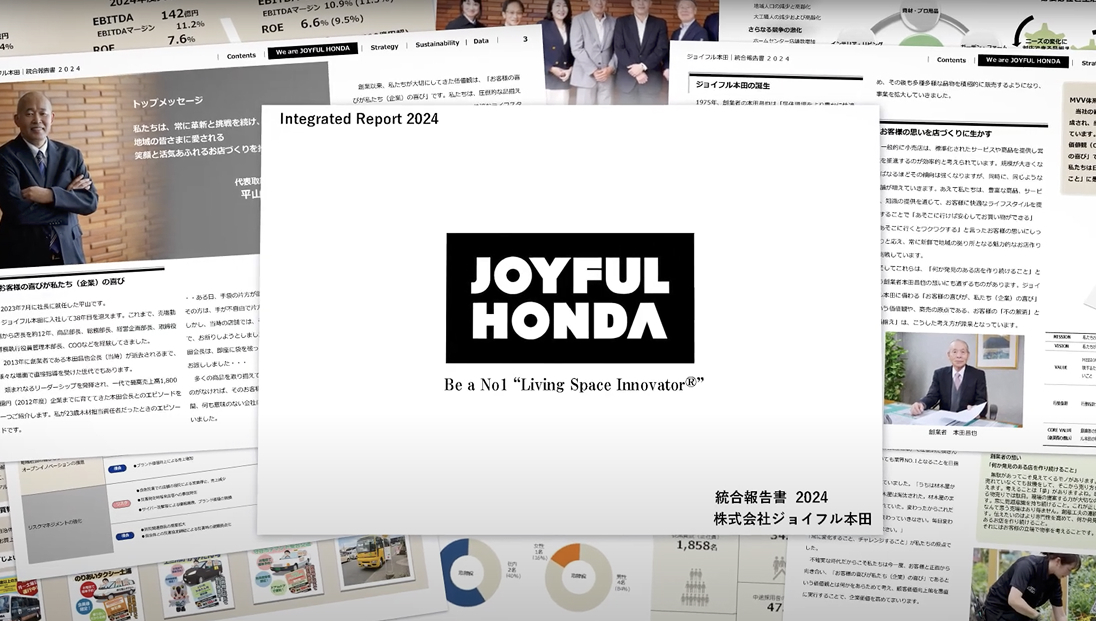
これまで以上に、
地域に「なくてはならない店」へ
地域の未来に向けた取り組みの展望について教えてください。
平山氏 : 地域にとって、より「なくてはならない施設」になることを目指したいです。そのためには必要なモノを届けることはもちろん、サービスもこれまで以上に充実させることが必要だと考えています。たとえば自転車が買えるだけでなく、長く使うために修理まで対応してもらえるなど、暮らしをトータルに支えていく存在になること。その先で高齢者支援など、より地域課題の解決につながる施策にも広げていきたいと考えています。

また災害が増加している近年は、非常時にどのように地域の方々を支えていくかということも重要だと考えています。たとえば行政における災害時の大きな課題は、住民の皆さんへ正しい情報をどう届けるかであるそうです。まだ計画段階ではありますが、当社の店舗が行政と連携して情報発信地としての機能も果たしていければと考えています。実際、現在も多くの店舗が地域の防災協定を結んでいますので、引き続き連携による取り組みを強化していたいと思います。

最後に、常陽銀行に期待することを教えてください。
平山氏 : 常陽銀行さんの大きな強みは、長く地域に根付き、中小から大手企業まで網羅的なつながりを持っていらっしゃることです。私たちの店舗だけでは得られない「地域がいま求めていることは何か?」といった、生きた質の高い情報を共有いただけることは、当社が地域の豊かな暮らしづくりを支えるための取り組みを行う上で非常に大きな力となっています。
一方、本質的な地域課題の解決に向けて当社だけでできることには限りがあるからこそ、他社さんとの連携が今後ますます重要になっていくと思います。常陽銀行さんが「地域の旗振り役」として、企業をつなぎ、協力し合える機会や場を設けてくださることをこれからも期待しています。



