NISAでの積立投資がマイナスになっているときはどうしたら良い?相場に振り回されない心構えとは

NISAは運用益が非課税になることから、投資初心者でも利用しやすい制度です。特に、一定の金額を定期的にコツコツ投資する積立投資は、少額から始められることや比較的リスクを抑えた資産形成ができることから、NISA初心者におススメです。一方、NISAでの積立投資は価格変動を伴うため、運用資産がマイナス評価になることもあり、資産が減る不安や恐怖を感じる人も多いのではないでしょうか。
しかし、資産がマイナスになっている場合に、焦って積立投資をやめてしまったり、資産を売却してしまうことは適切な行動とは言えません。
値動きに一喜一憂せず、まずは冷静になり、積立投資を続けるのが望ましいです。同時に、必要に応じて投資計画も見直しておきましょう。
この記事では、NISAでの積立投資がマイナスになっている場合の心構えや対処法を解説します。
目次
NISAで積立投資をしていてマイナスになったらどうしたら良い?

NISAで積立投資をしていて、資産がマイナスになっているとしても、積立投資は続けるのが望ましいです。マイナスになっている状況は、積み立てた金額よりも運用による評価金額が下がっている状態です。そのため、怖くなってすべて売却してしまったり、諦めて積立投資をやめようとしたりする人もいるでしょう。
しかし、マイナスになっているからといって積立投資をやめてしまっては、資産形成はうまくいきません。 マイナスになっている場合の対処法を解説します。
マイナスになっているときの考え方
NISAでの積立投資がマイナスのときには、以下の考え方を意識しましょう。
- 積立投資は長期的に行う
- 投資銘柄の値動きに一喜一憂しない
- マイナス相場を味方にする
NISAで積立投資をしていてマイナスになっていると、どうしても焦ってしまったり不安になったりしてしまうものです。メンタルの保ち方や考え方をおさえて、マイナスの際も平常心を保てるようにしましょう。
積立投資は長期的に行う
NISAで積立投資をする際は、あくまでも長期的に行うことを意識しましょう。長期的に積立投資を行うことで、価格変動のリスクを抑えることができ、また、複利効果も期待できます。
複利とは、投資によって得た利益を元本(積立金額)に組み込み再投資することで、さらに多くの利益を生んでいくことを指します。時間をかけて投資を続けることで、大きなリターンを得られる可能性が高まるのが特徴です。売却してしまうと複利効果を得られず、結果的に将来得られる可能性のあった利益を失ってしまいます。たとえマイナスになっていても投資は長期的に行うということを忘れないようにしましょう。
投資銘柄の値動きに一喜一憂しない
投資している商品・銘柄は日々価格が変動するため、価格が大きく変動している場合などには、値動きに一喜一憂しやすいです。
しかし、NISAで積立投資をする場合は、長期的に継続していくことが大事です。日々の値動きを気にしすぎて、途中でやめてしまったりすると、長期的な資産形成を妨げることになります。
積立投資は値動きよりも「毎月の積み立てが計画的にできているか」が重要です。短期的な値動きは長期的な積立投資では過度に気にすることはありません。
マイナス相場を味方にする
相場の下落局面は、投資した資産の評価がマイナスになっている場合もあり、早く回復してほしいという気持ちになる人も多いでしょう。
一方、下落局面にこそできることもあります。下落局面は投資する商品や銘柄の価格が下がるため、口数をより多く購入できます。下落局面の追加購入により、保有する口数を増やしておけば、相場が回復した場合には、その分の利益が期待できます。
将来的に資産を増やせる可能性を考えれば、下落局面でも通常どおり積立投資を続け、マイナス相場を味方にすることを考えてみましょう。
マイナスになっているときにしたいこと
NISAでの積立投資がマイナスのときには、以下の行動をとるようにしましょう。
- 変わらず一定額を積み立てし続ける
- 焦ってすぐに停止や売却をしない
- 分散投資ができているか計画を見直す
焦って感情的に行動するのは危険です。一旦落ち着いて、冷静に行動しましょう。
変わらず一定額を積み立てし続ける
積立投資では、資産の評価がマイナスになっていても、これまでと変わらず一定額を積み立てると良いでしょう。
資産の評価がマイナスの状況における、投資の続け方として知っておきたいのが、「ドルコスト平均法」です。ドルコスト平均法とは、価格変動のある商品を定期的に一定金額で買い付けていく投資の方法です。価格が高いときは少なく、価格が安いときは多く買い付けるため、平均購入単価の平準化が期待できます。
マイナスになっていても積み立てを続けることで購入単価が下がれば、再度相場が上昇した際に利益を得られる可能性が高まります。
焦ってすぐに停止や売却をしない
積立投資では、資産の評価がマイナスになっている状況に焦りを感じ「これ以上損失を拡大したくない」とすぐに積み立てを停止したり、資産を売却してしまうのは避けましょう。 とくに、株価などが急落してマイナスになっている際に、冷静な判断ができず、慌てて投資商品・銘柄を売却してしまう「狼狽売り」は避けたほうが良いでしょう。
相場の急落は驚きや恐怖などで感情的に判断してしまいがちです。一旦状況を整理し落ち着くことで、今後どのように積立投資を続けていくべきなのかを判断しましょう。
マイナスで売却してしまうと、NISAの恩恵である「運用益の非課税」を十分に享受できません。
例えば、米国の代表的な株価指数であるS&P500種指数のように、株価指数は上下しながらも、長期的には上昇を続けています。途中で投資をやめてしまうと、将来株価が上昇した場合には利益を逃すことにもつながります。
分散投資ができているか計画を見直す
積立投資を続けながら、投資計画を見直してみることも検討しましょう。
積立投資の資産評価がマイナスになる原因の1つが「特定の地域や特定の資産に偏っている」ことが考えられます。リスクを抑えたい場合に意識したいのは、分散投資です。分散投資とは、さまざまな資産や地域に投資対象を分散して、リスクとリターンを平準化する考え方です。
分散投資の重要性を示す例として、以下のような「卵をひとつのカゴに盛るな」という格言があります。
卵をひとつのカゴに盛るな

ひとつのカゴにすべての卵を入れると、そのカゴを落とした際にすべて割れてしまう。
しかし、いくつかのカゴに分けておけば、どれかひとつを落としても他のカゴの卵は手元に残る。
投資も同様に、複数の銘柄に分散して投資し、リスク管理をするのが大切なのです。
また、購入するタイミングを分ける「時間の分散」も大切です。時間を分散することで、価格が高いときは少なく、安いときは多く買えるため、購入単価の平均化につながります。積立投資の仕組を活用すれば、自然に「時間の分散」となり、投資期間が長くなるほど価格変動も安定します。
国内外のさまざまな地域に投資先を分けたり、異なる値動きをする資産(株式、債券、不動産など)を組み合わせたりすれば、ポートフォリオ全体の値動きが安定し、マイナスの状態が改善する可能性があるでしょう。
NISAでマイナスになったまま損切りした際のデメリット
NISAで積立投資をした資産がマイナスになった状態で売却(損切り)するデメリットとして、以下の2つが挙げられます。
- 元本割れで売却すると損が確定する
- 損失とほかの利益を相殺できない
マイナスになった際は、上記の点に十分注意しましょう。
元本割れで売却すると損が確定する
NISAで購入できる金融商品は、市場の状況や経済情勢に応じて価格が変動するリスクがあります。そのため、マイナス(元本割れ)になる可能性もあります。
「元本割れ」は、投資した金額よりも運用中の金額が減っている状態を意味します。この状態で投資商品・銘柄を売却すると、損失発生が確定してしまいます。また、NISAのメリットである「運用益の非課税」も享受できません。
積立投資の場合は、続けていれば相場回復時に利益が見込めるチャンスもあるため、元本割れでの売却は、本当に売却する必要があるのかをよく見極めてからにしましょう。
損失とほかの利益を相殺できない
NISA口座で発生した損失は、特定口座や一般口座といった、ほかの投資口座で出た利益とは相殺できません。通常の投資口座で損失が出た場合に利用できる以下のような制度は、NISA口座では利用できないため注意しましょう。
| 損益通算 |
|
| 繰越控除 |
|
NISAのメリットは運用益が非課税になるという点にあります。損失が発生した際は、ほかの投資口座同様の制度は受けられないため、損失が出ている場合の売却は慎重になったほうが良いでしょう。
NISAでマイナスになっていても積立投資を続けるメリット
NISAでの積立投資で、資産がマイナスになっていても積立投資を続けるメリットとしては、安値で買えて購入口数を増やせることや、平均購入単価を下げられることがあります。マイナスになっている状態では、投資する銘柄の基準価額も下がっています。そのため、相場が下落中のときは、下落前よりも安く買い付けられ、全体の平均購入単価を下げられるのです。 基準価額が平均購入単価を上回ると利益が生まれるため、平均購入単価を下げておくことで、将来的な利益が期待できます。
安く買い付けできれば保有口数が増えるため、下落局面で投資を中断していた場合と比べて、相場が回復した際に、多くの利益を見込める可能性があります。長期的に考えると、資産の増加が期待できるのです。
積立投資をするなら銀行NISAの利用がおススメ
NISAで積立投資をするなら、できれば利益を出して非課税のメリットを享受したいものです。しかし、資産のマイナスが続くと、いずれプラスになるのを期待していても、不安はなかなか消えません。
積立投資を成功させるなら、銀行でNISAを始めることも選択肢の1つです。銀行でNISAを始めるメリットを3つ解説します。
下落局面でも適切なアドバイスが受けられる
銀行でNISAを利用すれば、下落局面でもどのように乗り越えていけば良いのかアドバイスが受けられます。
銀行でNISAを利用する大きなメリットは、担当者に相談ができることです。下落局面で売ってしまって良いのか、このまま投資を続けて良いのかといった不安も、1人で悩まずに相談すれば適切なアドバイスがもらえます。金融のプロである銀行の担当者に、いつでも相談できるという安心感を持って運用したい方は、銀行でNISAを始めることを検討すると良いでしょう。常陽銀行では、店舗だけでなくオンラインでも相談を受け付けています。相談したいことがあるものの、店舗に出向く時間がないときにおススメです。
狼狽売りを避けられる
銀行でNISAを利用し、担当者のアドバイスを受けられれば、冷静な判断ができず慌てて資産を売却してしまう「狼狽売り」を避けられます。
ネット証券での取引では、資産管理や売買を1人でしなければなりません。そのため、急な下落局面が来た際にどのように対処したら良いか分からず、パニックになって資産を売却してしまう可能性があります。
しかし、銀行でNISAを利用すれば、担当者に相談して状況をよく理解できるため、焦って売ってしまうのを防げます。
投資計画を見直す際も適切なファンドが選べる
銀行でNISAを利用すれば、投資計画の見直しも相談でき安心です。
担当者のアドバイスをもとに、どういった銘柄を組み合わせていくか、リスク分散のためには何が足りないか、といったことを見直せるため、下落・急騰時はもちろん、いつでも気軽に相談ができます。
常陽銀行では、NISA対象の厳選されたラインナップはもちろん、1人ひとりのライフプランに応じたサービスを提供しています。個人の投資計画やライフプランのサポートが可能です。
NISAでマイナスになっている際のよくある質問
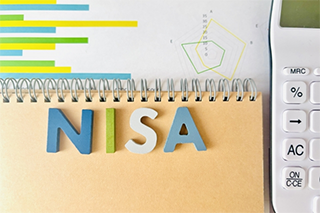
NISAでの積立投資で、資産がマイナス評価になっている際の質問・疑問をまとめました。相場下落時や値動きが激しく不安な際の参考にしてください。
NISAで積立投資をしてマイナスになる確率は?
NISAでの積立投資で、資産がマイナス評価になる確率を正確に予測することは誰にもできません。相場の動きはプロのアナリストでも読むのが難しいものであり、想定していた値動きとは反対の値動きになることも起こり得ます。
記事の中で紹介した「ドルコスト平均法」は、長期間一定金額で投資を続ける方法で、続けることで負けにくくなる投資方法です。
マイナスになる確率は予想できないものの、短期的な値動きに一喜一憂せず、リスクを平準化するために長期的にコツコツと積み立て続けるのが重要です。
NISAで積立投資をしていて1回でもマイナスになったら損失が確定する?
NISAで積立投資をしていてマイナス評価になることは十分にあり得ることで、一時的にマイナスになったからといって損失が確定するわけではありません。保有し続けることで、相場が回復し、プラスに転じる可能性も十分あります。むしろ、価格が下がっているときは、同じ投資額でより多くの口数を購入できるタイミングです。 相場が回復した場合に得られる利益が増えるよう、途中でやめずに積立投資を続けていくと良いでしょう。
NISAでマイナスが続くのが不安な場合どうしたら良い?
NISAでの積立投資で、資産がマイナスの状態が続き、精神的に不安な場合は、ファイナンシャル・プランナーなどお金の専門家に相談してみると良いでしょう。客観的なアドバイスを得たうえで、積み立てを続けていくなど適切な行動をとるようにしましょう。銀行なら資格を有した担当者に相談してアドバイスをもらえるため、マイナス局面も精神的に乗り越えやすいです。
また、過去の金融市場を振り返ると、大きな暴落があっても、時間はかかりながらも相場は回復してきた歴史があります。投資をやめてしまうのではなく、長く投資を続けたほうが、結果的に資産を増やせる可能性が高いと言えるでしょう。
NISAでの積立投資がマイナスになっても慌てない

NISAでの積立投資で資産がマイナス評価になることは、長期投資をしていれば何度も訪れる可能性があります。その際に、どのような心持ちでいたら良いか知っていれば、下落局面も落ち着いて乗り越えられます。自分自身で下落相場と向き合って乗り越えていくのが不安な人は、銀行でNISAを活用すると良いでしょう。
常陽銀行はスマホからNISA口座の開設ができ、開設後は窓口やオンラインで運用相談ができます。金融のプロが適切にアドバイスをしてくれるため、不安定な相場も担当者とともに乗り切れます。マイナスになっても長期目線で積み立てをし続け、資産を増やして将来に備えましょう。
(2025年8月27日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以上