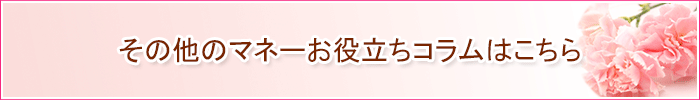大学の授業料はいくら必要?私立・国公立別4年間の平均や支払い時期も解説!
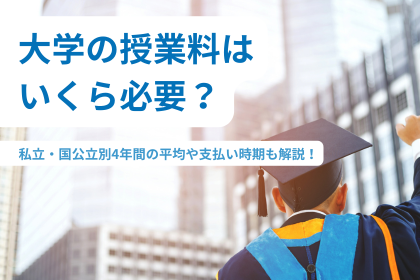
大学進学にかかる費用は、国公立大学で4年間約240~250万円、私立大学では学部により大きく異なりますが入学金や授業料、施設費などを含めて文系約400万円、理系で500万円超が目安です。また、授業料の支払い時期は、入学手続き時に初年度分を一括納付し、在学中は前期と後期の年2回に分けて支払うのが一般的です。
この記事では、学費の相場から支払いタイミング、奨学金や教育ローンの活用、さらに2025年開始の授業料無償化制度まで、最新情報をもとに分かりやすく解説します。
大学の授業料の相場と4年間の平均学費と入学金

大学進学にかかる学費は、国公立か私立かの大学の種類や学部によって大きく異なります。国公立大学は授業料が全国一律の「標準額」で設定されており、私立大学に比べて負担が抑えられる傾向があります。
一方、私立大学は大学や学部ごとに授業料や入学金が異なり、文系・理系・医歯系など分野によっても大きな差があります。
目安として、4年間に必要な学費総額の平均は以下の通りです。
| 大学種別 | 入学金(初年度) | 年間授業料(年額) | 4年間合計(学費総額) |
|---|---|---|---|
| 国立大学 | 約28万円 | 約53万円 | 約242万円 |
| 公立大学(地域内) | 約22万円 | 約53万円 | 約236万円 |
| 公立大学(地域外) | 約38万円 | 約53万円 | 約251万円 |
| 私立大学(文系) | 約22万円 | 約82万円 | 約410万円 |
| 私立大学(理系) | 約23万円 | 約116万円 | 約541万円 |
| 私立大学(医歯系) | 約107万円 | 約286万円 | 約1,605万円 |
| 私立大学(その他) | 約25万円 | 約97万円 | 約508万円 |
国公立大学は4年間で約240~250万円と私立に比べて学費負担が小さく、私立大学は文系でも約400万円、理系では500万円以上かかります。
特に医学部・歯学部など6年制の学部では学費が突出して高額(合計1,600万円超)になる点に注意が必要です。
国公立大学4年間の平均学費総額
国立大学の場合、入学金と授業料は国の省令で定められた「標準額」で全国ほぼ共通です。2024年度現在、標準額は入学金28万2,000円、授業料53万5,800円(年額)と定められています。
年に53万5,800円が4年かかる計算で4年間の授業料総額は約214万円、これに入学金を加えた4年間の総額は約242万5,000円になります。
公立大学の場合、国立大学と大きな学費の差はありませんが、入学金については出身地域によって差があります。多くの公立大学では、在住自治体の納税者である「地域内生」には入学金を減額する制度があり、地域内入学者の入学金平均は約22万5,000円、地域外入学者では約38万8,000円になっています。
授業料は国立大学とほぼ同額で、平均すると年間53~54万円程度です。
私立大学4年間の平均学費総額
私立大学の学費は大学や学部によって千差万別ですが、平均的な初年度納入金(入学金+初年度授業料+施設設備費等)は約147万7,000円となっています。
年に96万円が4年かかる計算で4年間の授業料総額は約384万円、これに入学金と施設設備費等を加えた4年間の総額は約474万円になります。
- 入学金:約24万円
- 授業料:約384万円
- 施設設備費:約66万円
計:474万円
学費総額は学部によって大きく異なるのが私立大学の特徴です。例えば、医学部・歯学部などの医歯系学部では6年間で2,300万円以上となっています。
| 大学種別 | 入学金(初年度) | 年間授業料(年額) | 4年間合計(学費総額) |
|---|---|---|---|
| 私立大学(文系) | 約22万3,867円 | 約82万7,135円 | 約410万8,000円 |
| 私立大学(理系) | 約23万4,756円 | 約116万2,738円 | 約541万8,000円 |
| 私立大学(医歯系) | 約107万7,425円 | 約286万3,713円 | 約1,605万4,000円 |
| 私立大学(その他) | 約25万1,164円 | 約97万7,635円 | 約508万9,000円 |
上表の通り、私立大学の文系では4年間で約410万円、理系では約542~1,606万円ほどが平均的な目安になります。
大学の授業料はいつ支払う?

まず、入学手続き時に入学金と初年度前期分の授業料をまとめて納めるのが一般的です。多くの大学ではその後、前期分(4月)と後期分(9~10月)に分けて年2回支払う形式を採用しています。
なお、入学時に支払う初年度納入金は学費の約6~7割に相当する大きな金額となるケースが多いです。国公立大学でも入学時に約60万円前後、私立大学の文系・理系では80~100万円前後を一括で納める必要があります。
大学によって分割払いや延納制度が用意されていることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
大学の授業料以外に必要な費用

大学では、入学金や授業料の他にも必要になるお金がたくさんあります。以下では、具体的に必要になるお金の種類とその金額についてお伝えします。
賃貸やアパートなどの契約金
遠方の大学に進学し、学校に寮などの準備がない場合は賃貸やアパートの契約が必要になります。
そして、部屋を契約する際には、敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料なども必要です。契約時に、1カ月分の家賃を前払いするケースも多いので、敷金礼金とあわせると、家賃3カ月分くらいがかかると考えておくと良いでしょう。物件によっては、敷金礼金を徴収されないところもあるので、そういった物件を選ぶと費用を抑えることができるでしょう。
学校が寮を持っていて、そこへの入居が可能なのであれば、費用を大きく抑えることができます。寮の有無も確認しておくと良いでしょう。
家具などの生活用品にかかるお金
初めての一人暮らしであれば、家具や生活用品をそろえる必要があります。ドライヤーのように小さなものから、大きなものであれば冷蔵庫まで、様々な家具や家電が必要です。
一人暮らしであれば冷蔵庫や洗濯機のサイズは小さめで問題ありません。家電量販店に行けば、生活ができるだけの家電をまとめて安く販売するセットもあります。このような商品を利用することで安く済まそうと思えばかなり価格を抑えることも可能です。
トイレットペーパーや、掃除道具などのこまごました日用品もあわせると15万円ほどで揃えられるでしょう。
引越し代
初めての一人暮らしであれば、新しく買うものが多いので実家から持ち出すものは少ない場合が多いでしょう。そのため自家用車や、レンタカーで運んで済ませてしまう人も多いようです。そうなれば、引越し業者に依頼するよりも費用を抑えることができます。
実家の家具を持って行くなどで荷物が多いケースは、引越し業者に搬送を依頼する必要があります。様々な料金体系の引越し業者がありますが、単身で荷物が平均的な量なのであれば、かかる費用は4万円ほどで収まると考えて問題ないでしょう。
しかし2~4月にかけては、入学・卒業・就職・転勤などの様々な理由で引越し業者を利用する人が多く、価格が高騰します。そのような繁忙期では費用が5万円以上かかることもあります。
家族で車を出したりレンタカーを借りたり、すぐに必要なものでなければ、配送で送ってしまうなど、費用を抑える工夫もできるので、荷物の量に見合った方法を探してみてください。
毎月の家賃やその他の費用
毎月の家賃や、光熱費なども生活費として欠かせません。
家賃は、契約にもよりますが、2年に1回のペースで家賃の1カ月分ほどの更新料がかかるケースがあります。更新時にかかるお金なので、すぐに準備する必要はありません。しかし4年間学校に通う場合は、その更新料もかかる金額として考えておかなければなりません。
また、電気代や水道代、ガス代などの光熱費は、一人暮らしだとすべてあわせて1カ月で10,000~15,000円くらいかかってくると考えれば良いでしょう。
また、インターネットや携帯電話の使用料金などの通信費もかかります。最近では格安SIMを利用して通信費を抑える方法もありますので、検討してみても良いかもしれません。
娯楽費
新しい学生生活が始まると、新しい友人もできるでしょう。そうなれば、一緒に出かける機会も増え、それに伴って、交際費、娯楽費もかかります。
さらにサークルなどに所属すると、サークル活動費としてもお金が必要になるため、そこも考慮しなければなりません。
大学生の交際費や、娯楽費は月平均で2万円と言われていますが、もちろん人との付き合い方によって大きく異なってきます。
交際費や娯楽費に関しては、自分でアルバイトしたお金でまかなうなどと決めている家庭も多いようなので、家族で話し合って決めるのが良いでしょう。
交通費や教材費
また、学校に通うための交通費や、授業で使う教科書や参考書などの教材費も必要となります。
電車やバスなどの公共交通機関を利用するのであれば、定期券の購入で、1カ月の交通費を少し抑えることができます。
バイクや、車、自転車での通学が許可されている学校であれば、それらを使って通学することができますが、その場合ガソリン代や車両の維持費がかかってきます。
家と大学が近ければ近いほど学校への交通費は抑えられるので、物件を探す段階から交通費を考えておくのがおススメです。
教材費は、大学の授業で使われるような専門書は、一般書よりも価格が高いことがほとんどです。学部にもよりますが、辞書のような教材が必要な学部もあるので教材費だけで数万円もかかるなどということもあります。どれくらいかかるのか、あらかじめ調べて、把握しておきましょう。
インターネットで調べてみると、もう使わなくなった人や卒業生が参考書を出品している場合があるので古本で探してみるのも費用を抑えるには良い方法です。
留学する場合の費用
また、お子様が留学を希望した場合は留学の費用も必要です。語学系の学校に進学するのであれば、留学も視野に入れて、費用を把握しておきましょう。
留学にはいろいろな種類がありますが、学校を休学して、海外の学校に留学するケースでは日本の大学の授業料を支払いながら現地の授業料も支払うことになります。その場合は大きな資金が必要になります。
日本の学校と現地の学校にもよりますが、留学代理店が公開している情報によるとアメリカに留学した場合は、1年間で200~400万円ほどかかるとされています。
留学してからの食費や交際費なども、現地の物価に見合った金額がかかってきます。
また、大学によっては留学の制度が用意されています。交換留学制度などを利用すると現地の学校への授業料の免除や、返済が不要な奨学金を借りることができるケースもあります。そういった制度を利用することで費用を大幅に抑えられるので、留学を検討している場合は調べてみましょう。
大学の授業料を貯める・借りることを検討する
前もってお子様の希望を聞いていれば、進みたい学校や学部の種類が分かってきます。そこから、必要になるおおよその費用を計算し、必要になるタイミングに間に合うように計画的に資金を準備しましょう。
さらに奨学金を利用したり、国の教育ローンを利用するの1つの方法です。
奨学金として最も有名なのが、「独立行政法人日本学生支援機構」の奨学金制度です。
日本学生支援機構の奨学金は、卒業後に返還していく貸与型の奨学金です。卒業後は親が返していくのか、本人が返していくのか話し合いをしておきましょう。なお、奨学金は入学後に振り込まれるケースが多いので、入学金については別の方法で準備する必要があります。
一方、教育ローンには、国による融資制度と金融機関が行う2種類が存在します。国による融資制度は、公的な制度なので、家庭の所得にまつわる一定の条件が設けられていることが特徴です。
一方で、金融機関による教育ローンは国の教育ローンよりも使い道や審査の基準が厳しくないことが多いのが特長です。申し込みの条件は金融機関によって様々なので複数の教育ローンをチェックしてみると良いでしょう。
また、奨学金と教育ローンを併用するという方法もあります。初年度の入学金は教育ローンで準備し、その後の学費は奨学金を活用するなど、組み合わせも検討してみましょう。
大学の授業料に関するよくある質問
大学の授業料無償化はいつからですか?
2025年から子どもを3人以上扶養している多子世帯の大学生を対象に、所得制限なしで授業料が全額免除される新制度も追加され、対象が拡大されます。ただし、扶養される子どもが3人以上同時に扶養されていなければいけない点に注意しましょう。また、補助の上限もあるため超える分に関しては自己負担が必要になるケースもあります。
大学4年間の学費はいくらですか?
大学の4年間の学費は、国公立か私立か、また学部によって大きく異なります。国公立大学の場合、授業料と入学金を合わせて約240~250万円程度が一般的です。一方、私立大学では文系で約400万円、医・歯学部除く理系学部では500万円以上かかるケースが多いです。
大学の授業料は子ども3人目からどうなりますか?
2025年4月から、子どもを3人以上扶養している世帯の大学生は、所得制限なしで授業料と入学金が全額免除される制度が導入されます。扶養条件や在籍状況などの要件を満たす必要があるため、条件は必ず確認しておきましょう。
まとめ

お子様の大学進学に必要なお金や、入学後に必要なお金を解説しました。
選ぶ学校の種類によってのおおよその費用や、資金調達の方法についてお伝えしましたが、計画的に資金計画を立てる必要があるとお分かりいただけたかと思います。
教育ローンを検討されている方には、常陽銀行の教育ローンをおススメします。常陽銀行の教育ローンなら、引越し費用や留学資金にもご利用可能で最大1,000万円までお申し込みができます。また、保証料が無料などのメリットがあります。来店せずにスマホやパソコンからお申し込みいただけますので、ぜひご検討ください。
教育ローンについてはこちら(2025年8月8日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以 上