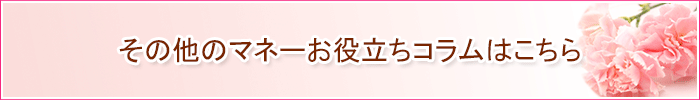運転免許の種類・取得方法・費用について:取得費用を抑える方法とは

運転免許とは?

運転免許とは、自動車やバイクなど、一定の技量が求められる機械の運転に必要な免許のことで、国の法律によって認められた国家資格の1つです。自動車の運転免許は一般道路を安全に走行するために必要な技量と知識を習得した人に対して発行され、運転免許を取得することで、日本の公道で車を運転することができるようになります。また、免許の保有が証明されると運転免許証が交付されます。
この記事では、自動車の運転免許の種類と取得方法、運転免許を取得するためにかかる費用の内訳や費用を抑える方法について解説します。
運転免許の種類
自動車の運転免許には「第一種運転免許(一種免許)」「第二種運転免許(二種免許)」「仮運転免許(仮免)」の3つの区分があり、主に以下のような違いがあります。
| 第一種運転免許 | 自動車や原動機付自転車を運転するために必要な免許 |
|---|---|
| 第二種運転免許 | タクシーやバスなど、営利目的で客を運送するために必要な免許 (自家用バスやレンタカーは除く) |
| 仮運転免許 | 運転免許の取得を目的とする教習生に仮交付される免許 |
運転免許は運転する自動車によってさらに細かく分かれ、運転する自動車の種類に合わせて免許を取得する必要があります。ここでは、第一種運転免許の種類を中心に解説します。
| 運転できる車の種類 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免許の種類 | 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 大型特殊自動車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 | 牽引自動車 |
| 普通免許 (AT限定免許を含む) |
○ | ○ | ○ | |||||||
| 準中型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 中型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小型特殊免許 | ○ | |||||||||
| 大型特殊免許 (カタピラ車限定免許を含む) |
○ | ○ | ○ | |||||||
| 原付免許 | ○ | |||||||||
| 大型二輪免許 (AT限定免許を含む) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 普通二輪免許 (AT限定、小型二輪限定、AT小型限定免許を含む) |
○ | ○ | ○ | |||||||
| 牽引免許 (小型トレーラー限定免許を含む) |
○ | |||||||||
自動車や原動機付自転車を運転するために必要な第一種運転免許の種類は上表のとおり、全部で10種類です。免許の種類によって運転できる車が異なります。
第一種運転免許の中でも取得者が多いのが「普通免許」で、普通自動車の免許取得後は普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転が可能になります。
普通免許は運転する車によって「MT(マニュアル)」と「AT(オートマ)」に分かれています。MTとATでは運転操作が異なるため、普通免許を持っているとMT車・AT車両方を運転することができますが、普通免許AT限定の場合は、AT車のみ運転することができ、MT車は運転することができません。
第一種運転免許の受験資格
| 運転免許の種類 | 年齢における受験資格 | 視力における受験資格(眼鏡等使用可) | 経歴における受験資格 |
|---|---|---|---|
| 大型免許 | 21歳以上 |
|
|
| 中型免許 | 20歳以上 |
|
|
| 準中型免許 | 18歳以上 |
|
|
| 大型特殊免許 | 18歳以上 |
|
なし |
| 小型特殊免許 | 18歳以上 |
|
なし |
| 大型二輪免許 | 18歳以上 |
|
なし |
| 普通二輪免許 | 16歳以上 |
|
なし |
| 普通免許 | 18歳以上 |
|
|
| 原付免許 | 16歳以上 |
|
なし |
第一種運転免許の受験資格については上表のとおりです。免許の種類を問わず、それぞれ年齢と視力に制限があり、大型免許や中型免許などはさらに特定の経歴や他免許を取得していることが条件となります。
取得者が最も多い普通免許は、18歳以上で、両眼で視力が0.7以上あること(左右それぞれ0.3以上)が条件です。また、普通仮免許(または準中型・中型・大型仮免許のいずれか)を取得しており、過去3カ月以内に5日以上、一般道路で運転の練習をしている必要があります。
運転免許証の色の見方
| 免許証の色 | 内容 | 運転者区分 | 年齢 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|
| グリーン | 初めて運転免許証を取得した運転者に交付 | なし | 年齢問わず | 3年間 |
| ブルー | グリーン免許から初めて更新する際や、過去5年間に軽微な違反(3点以下)の運転者に対して交付 | 一般運転者 | 70歳未満 | 5年間 |
| 70歳 | 4年間 | |||
| 71歳以上 | 3年間 | |||
| 違反運転者 | 年齢問わず | 3年間 | ||
| 初回更新者 | 年齢問わず | 3年間 | ||
| ゴールド | 有効期限満了日から前5年間、無事故・無違反の運転者に交付 | 優良運転者 | 70歳未満 | 5年間 |
| 70歳 | 4年間 | |||
| 71歳以上 | 3年間 |
運転免許証は、運転者の運転経歴などがひと目で分かるよう、有効期限が記載されている部分がグリーン、ブルー、ゴールドの3色に分かれています。
グリーンは免許取得から3年未満の運転初心者の色で、ゴールドは5年間無事故・無違反の「優良運転者」の色、ブルーはそれ以外の「初回運転者」(免許を初めて更新した人)、「一般運転者」(免許取得から5年が経過しており、その間軽微な違反が1回だけの人)、「違反運転者」(複数回の違反があった人)の色となっています。
運転免許証の点数制度
点数制度とは、交通違反を繰り返す人の運転を制限することを目的に、運転者の交通違反や交通事故に対し、危険度に応じて点数をつける制度です。この点数制度には減点方式ではなく「累積方式」が採用されており、運転中に警察から違反があったとみなされた場合、違反の危険度によって都度点数が加算されます。
点数はドライバーの違反回数や違反の危険度を表すものであり、過去3年間の累積点数が多い運転者に対しては免許の停止や取消等の処分が行われます。
| 交通違反の種別 | 違反点数 | 普通車の反則金額 | |
|---|---|---|---|
| 特定違反行為 | 運転殺人等・危険運転致死 | 62点 | 刑事罰が科せられる |
| 運転傷害等・危険運転致傷 | 45点~55点 | ||
| 酒酔い運転・麻薬等運転・救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 | ||
| 速度超過 | 【一般道】30km以上50km未満 | 6点 | 刑事罰が科せられる |
| 【高速道】40km以上50km未満 | 6点 | ||
| 【高速道】35km以上40km未満 | 3点 | 35,000円 | |
| 【高速道】30km以上35km未満 | 3点 | 25,000円 | |
| 25km以上30km未満 | 3点 | 18,000円 | |
| 20km以上25km未満 | 2点 | 15,000円 | |
| 15km以上20km未満 | 1点 | 12,000円 | |
| 15km未満 | 1点 | 9,000円 | |
| 携帯電話使用等 | 交通の危険 | 6点 | 刑事罰が科せられる |
| 保持 | 3点 | 18,000円 | |
| 泥はね運転 | - | 6,000円 | |
| 公安委員会遵守事項違反 | - | 6,000円 | |
| 運行記録計不備 | - | 4,000円 | |
| 警音器使用制限違反 | - | 3,000円 | |
| 免許証不携帯 | - | 3,000円 | |
交通違反は比較的軽度な「一般違反行為」と危険度の高い「特定違反行為」に分けられており、違反をすると、点数の加点と反則金の支払い、2つの罰則が発生します。反則金は違反の内容によって変動し、主な金額は上表のとおりです。
一般違反行為の代表的なものは「速度超過」「駐車違反」「指定場所一時不停止等」「シートベルト装着義務違反」「信号無視」などで、1点~6点がほとんどです。危険度の高い違反、時速50km以上の速度超過や酒気帯び運転などについては12点以上が加点されます。また、2019年の法改正により、運転中に携帯電話を使用する「ながら運転」への処分が重くなりました。携帯電話の通話や注視により交通の危険を引き起こした場合、6点減点で免許停止、かつ1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
特定違反行為の代表的なものには「酒酔い運転」「麻薬等運転」「救護義務違反(ひき逃げ)」「運転傷害等」「運転殺人等」が該当し、35点~62点の加点となります。
また、違反行為が軽微な場合は「交通反則告知書(青切符)」と反則金仮納付書が発行され、指定期日までに反則金を納付すれば前科はつきません。しかし、反則金を納付しなかった場合、最終的には裁判所や検察庁で裁判になります。無免許運転や酒気帯び運転など重い違反を犯した場合は、赤切符が切られて刑事罰が科せられ、裁判で判決が下されると罰金額が決まり、前科がつきます。
運転免許を取得する方法は?
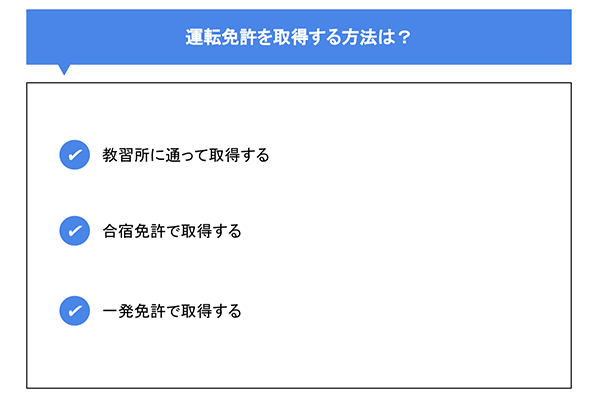
自動車を運転するための免許の取得方法はいくつか選択肢があります。「自動車教習所に通う」「合宿教習を受ける」「免許センターで直接試験を受ける」の主に3つです。
ここでは、この3つの免許取得方法について解説していきます。それぞれメリット・デメリットがあるため、自分に合った取得方法を検討することが大切です。
教習所に通って取得する
自動車の運転免許の取得には、自動車教習所に通って講習や技能の指導を受けるのが一般的です。自動車教習所では、運転に関する知識や運転技術を学ぶことができ、自分の都合に合わせて通うことができます。教習所で取得する免許は「教習所免許」と言われています。
教習所には、法令に基づき公安委員会が指定した「指定教習所」とそれ以外の自動車教習所があり、できることに差があります。指定外の自動車教習所では仮免許の技能試験が受けられず、免許センターまで行かなければならないケースなどもあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
合宿免許で取得する
自動車教習所に通う以外に、合宿所やホテルなどの施設に滞在しながら教習所に通って免許を取得する方法があり、こちらは「合宿免許」と呼ばれています。教習所通いとの違いは、教習スケジュールがあらかじめ決まっており、合宿所に滞在しながら集中して教習を受けることで、約2週間という短期間で、教習所に通うよりも費用を抑えて免許が取得できる点です。
学生などまとまった休みをとりやすい人の利用が多く、滞在する合宿所によっては旅行気分を味わえるため、若い年齢層を中心に人気です。
一発免許で取得する
教習所免許や合宿免許のほかに、「一発免許」と呼ばれる免許があります。これは、事前に自動車教習所で講習や技能教習を受けず、運転免許試験場(免許センター)で直接学科試験・技能試験を受ける「一発試験」とも言われている方法です。試験合格後、運転免許取得時講習を受講し、免許センターに申請することで免許証が交付されます。
一発免許は過去に免許を取得していたことがあり、有効期限の失効や免許の取り消しなどで免許を失った人が、再度免許を取得する際に利用している方法です。技能試験の免除がなく、一度に「仮免許学科試験」「仮免許技能試験」「本免許学科試験」「本免許技能試験」すべてに合格する必要があるため難易度が高く、初めて免許を取得する方にはおススメできません。
運転免許にかかる費用とは
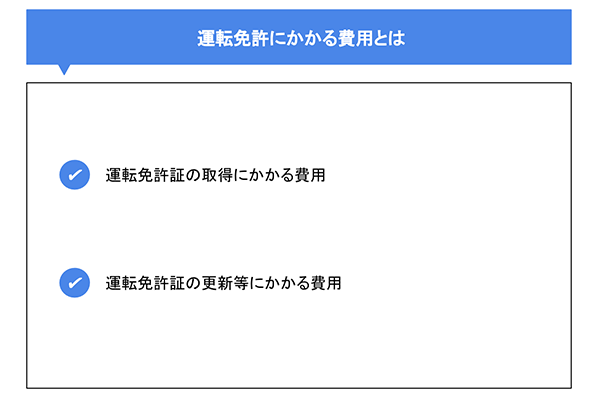
運転免許・運転免許証を取得するには費用がかかります。また、免許取得後数年が経ち、免許証を更新するときには更新費用が、免許証を紛失した場合は再発行するための手数料がかかります。
ここでは、教習所、合宿、一発試験の3つの方法で免許を取得した際にかかる費用と、免許証にかかる費用について解説していきます。
運転免許証の取得にかかる費用
免許取得にかかる費用は、免許の取得方法により異なり、主に「教習所や合宿での教習費用」と「受験・免許交付にかかる費用」に分けることができます。
自動車教習所の場合、各教習所の料金設定によって違いはありますが、普通免許のコースを最短で卒業した場合、かかる費用の相場はAT車限定免許は約24~33万円(二輪免許所持の場合は約18~29万円)、MT免許は約25~34万円(二輪免許所持の場合は約20~30万円)が一般的です。卒業までの期間が必要以上に長引けば費用はこれ以上かかることになります。
一方、合宿免許は短期間のため、最大35万円弱かかる教習所と比べると低予算に抑えることができ、相場は約15~25万円です。ただし、合宿の場合は施設やプランによって価格差が出るため、内容によっては想定していた予算より高額になることもあります。
自動車教習所、合宿の場合は、その後、本免許学科試験の受験費用として1,750円、試験に合格すると免許証交付手数料2,050円がかかります。
一発試験で免許を取得する場合は学科講習や技能教習がないため、すべての試験に一発で合格した場合、必要となる費用は合計2万6,300円です。
運転免許証の更新等にかかる費用
| 区分 | 更新手数料 | 法定講習手数料 | 計 |
|---|---|---|---|
| 優良運転者 | 2,500円 | 500円 | 3,000円 |
| 一般運転者 | 800円 | 3,300円 | |
| 違反運転者 | 1,350円 | 3,850円 | |
| 初回更新者 |
※2020年1月現在
自動車の運転免許証には有効期限が設けられており、免許証の更新には費用がかかります。内訳は更新手数料と法定講習手数料の合計金額で、更新手数料は一律2,500円、法定講習手数料は、運転者の区分によって上表のように変わります。高齢者講習、特定任意高齢者講習・特定任意講習、運転免許取得者教育(高齢者講習同等/更新時講習同等)などを修了している場合は法定講習を受講する必要はありません。
また、運転免許証の破損や紛失の際の再交付には、手数料が2,250円かかります。住所、本籍地の変更など、記載事項変更届を出して内容を変更する場合は無料です。
運転免許取得にかかる費用を抑えるには?
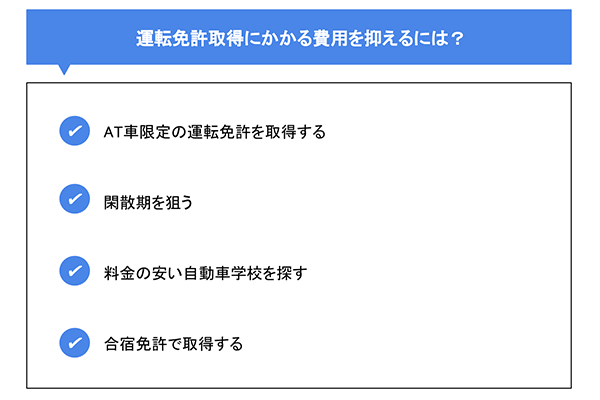
自動車の運転免許を取得するために必要な費用は、教習所代と、受験などそれ以外の諸費用です。そのうち、費用をある程度抑えることができるのは教習所にかかる費用です。
ここでは、運転免許取得にかかる費用を抑える方法について解説していきます。
AT車限定の運転免許を取得する
普通自動車の運転免許を取得する場合、MT車とAT車限定があり、AT車限定は技能時間が少ない分、費用を抑えることができます。MT車を乗る予定がないようであれば、AT車限定の免許をとると、ある程度は費用を抑えることができます。
閑散期を狙う
自動車教習所や合宿教習は、夏休みなどの長期休暇があるときは希望者が多く混雑しています。逆に、人が多く集まる時期を外して閑散期を選べば、料金設定が変わる場合もあります。ある程度のスケジュール調整が可能で時間に余裕があるのであれば、空いている閑散期を狙って入校を申し込むのも1つの方法です。
料金の安い自動車学校を探す
自動車教習所の料金設定は一律で決まっているわけではなく、それぞれの施設によって料金設定は異なります。地域で人気の教習所などは料金設定が高いこともあるので、何校か資料を取り寄せて料金の比較をしてみることも必要です。また、学生割引など割引特典を使える場合もあるのでチェックしてみると良いでしょう。
合宿免許で取得する
短期間で集中的に教習を受け、運転免許を取得することが可能な合宿免許。教習所に通った場合と比べ、最大20万円前後の費用を抑えることができます。約2週間のスケジュール調整が必要となりますが、低予算で免許を取得したいという方にはおススメです。
免許取得の資金が足りないならローンという選択肢も

自動車の運転免許の取得には、最大35万円程度の費用がかかります。免許の取得が事前に分かっているようであれば、計画的に費用を貯蓄しておくのが理想ですが、転勤や転職などで急に運転免許が必要となるなど、やむを得ない事情ですぐに運転免許を取得しなければならないこともあるかもしれません。
運転免許取得のための資金が足りない、そんなときは、マイカーローンを組むという選択肢もあります。
常陽銀行のマイカーローンは、免許の取得を始め、免許取得後に乗る車の購入など、車に関する用途に幅広く利用することができるローンです。繰上返済手数料や保証料は無料です。銀行に行かずにスマホやパソコンで契約が可能な商品となっています。早く免許が欲しいのに資金を用意する時間がない、という方は、まずは借り入れ可能額がすぐに分かる「5秒診断」をお試しください。
常陽マイカーローンについてはこちら
(2020年9月29日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以 上