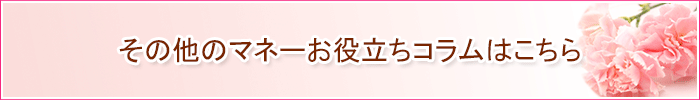育児休業給付金で生活費に余裕を。条件を満たして忘れず申請しよう
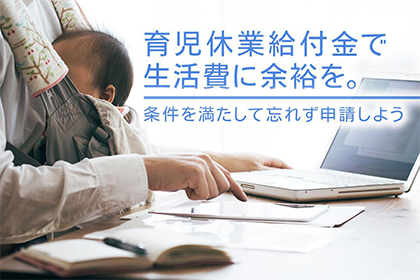
子どもが生まれると、育児のために働けない期間があります。その間は収入が下がってしまい、大変な思いをする方もいるのではないでしょうか。
そこで活用してほしい制度が「育児休業給付金」です。この記事では育児休業給付金について解説します。給付の対象条件や支給額、申請方法などについて深掘りしますので、育児休業給付金の利用を検討したい方はぜひ参考にしてください。
育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育児休業を取得する被保険者が受けることができる給付金のことです。育児休暇を取得してから、子どもが1歳になるまでの間に受け取れます。
ただし、受給するにはいくつかの要件を満たす必要があり、労働者全員が給付できるわけではありません。
育児休業給付金の基礎知識

まずは育児休業給付金の基本的な内容について解説していきます。
育児休業給付金の受給要件
育児休業給付金の受給要件は以下のとおりです。
- 雇用保険の被保険者であること(育児休業給付金は雇用保険から給付されるため)
- 育児休業を開始した日から2年間、就業日数が11日以上の月が12カ月以上あること
- 育児休業の就業日数が各1カ月に10日以下であること
- 育児休業後も在職している職場で就業予定であること
- 育児休業中に支払われる1カ月の賃金が、休業前の賃金の8割未満であること
もし12カ月に満たない場合でも、本人の疾病などの事由によっては受給要件が緩和されることもあります。
産後休業から育児休業をとった女性の場合、育児休業開始日は出産日から数えて58日目とします。また女性に限らず、男性も育児休業給付の対象です。
なお、2022年10月から育児休業給付制度が変わることがアナウンスされています。
- 1歳未満の子どもがいる家庭では、原則として2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられる
- 子どもが生まれてから8週間以内の間に「産後パパ育休」として、4週間まで産休が取得できる
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金を取得できる場合、支給額はいくらになるのでしょうか。ここでは育児休業給付金の支給額の計算方法を紹介します。
育児休業給付金の支給額は1カ月ごとに計算します。
休業開始~6カ月以内:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×0.67
休業開始~6カ月以降:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×0.5
休業開始時賃金日額は事業主がハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」に基づいて計算されます。計算式は以下のとおりです。
休業開始時賃金日額:育休開始前(※)6カ月間の総支給額÷180
- 女性は産休開始前からカウントする
また育児休業給付金には、支給期間である1カ月単位で上限と下限が設けられています。育児休業給付金額の計算に使われる「休業開始時賃金月額」の上限と下限はこちらです。
- 休業開始時賃金月額の上限:45万600円
- 休業開始時賃金月額の上限:7万7,310円
休業開始時賃金月額に育児休業給付金の支給時期で異なる数字をかければ、1カ月当たりの上限額と下限額が計算できます。
- 6カ月以内の上限額:30万1,902円
- 6カ月以降の上限額:22万5,300円
- 6カ月以内の下限額:5万1,797円
- 6カ月以降の下限額:3万8,655円
この上限額と下限額は2022年6月現在の数字です。毎年8月に改定されるので、あくまでも参考程度にしてください。
育児休業給付金の支給のタイミング
育児休業給付金の申請をしても、すぐには支給されません。また、審査に通らなければ支給されず、審査には通常2週間程度かかります。そのため、初回の給付は申請から4〜5カ月かかることもあります。
2回目以降は審査が不要のため、基本的には2カ月に1回支給申請をして振り込まれる流れです。被保険者本人が希望すれば、1カ月ごとに申請もできます。
育児休業給付金を申請する流れ
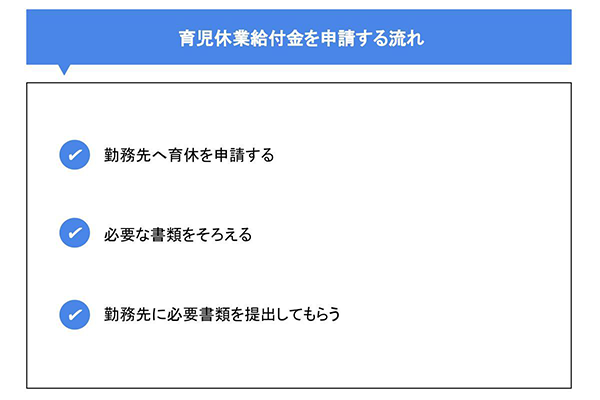
育児休業給付金の受給条件を満たしていれば、申請手続きを行いましょう。何かと大変な育児休業中。あらかじめどのような手順で進めるのかを把握しておくと、スムーズに手続きができます。
勤務先へ育休を申請する
育児休業給付金の支給には書類が必要です。書類は事業主がハローワークに申請しなければ発行してもらえません。
育休を取得することを決めたのなら、まずは勤務先に報告してください。実際には人事や労務が手続きをするのですが、一般的には上司に相談することになるでしょう。
上司が人事や労務にかけあって手続きを進めるのか、または上司を通して育休の申請をするのかは勤務先によって異なります。これからどのように手続きを進めていくのか、疑問点があれば聞いておきましょう。
必要な書類をそろえる
育児休業給付金の支給に必要な書類を用意します。初回と2回目以降とでは必要書類が異なります。
初回の申請に必要な書類
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金の額や支払い状況が証明できる書類(賃金台帳や労働者名簿、タイムカードなど)
- 育児をしている事実を確認できる書類(母子手帳など)
2回目以降の申請に必要な書類
- 育児休業給付支給申請書
- 申請書に記載された支給対象期間中に支払われた賃金の額や支払い状況、休業日数および就労日数を確認できる書類(賃金台帳や出勤簿、タイムカード)
受け取った書類には記入欄があるので、申請者本人の直筆で記入してください。育児休業給付金支給申請書は初回と2回目以降の申請でも必要ですが、記載内容は異なります。内容を確認して記入しましょう。
勤務先に必要書類を提出してもらう
すべての書類がそろったら、勤務先に必要書類を渡してください。勤務先が事業所の所在地を管轄しているハローワークに提出して、手続きは完了です。
申請は2カ月に一度行う必要があります。基本的には勤務先が必要書類を申請してくれますが、申請者本人が行っても構いません。
ハローワークは平日の朝から夕方まで開いています。開庁時間は場所によって異なります。土曜日も開庁しているハローワークもあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
育児休業給付金の延長制度

通常、育児休業給付金の支給期間は1年と定められています。しかし一定の条件を満たせば、育児休業給付金の支給期間が延長できるのです。ここからは、育児休業給付金の延長制度について解説していきます。
育児休業給付金が延長できる条件
育児休業給付金が延長できる条件は以下のとおりです。いずれかの条件に該当した場合、適用の対象になります。
-
保育所(※)などに入所の申し込みを行っているものの、子どもが1歳に達しても当面保育の実施が見込まれないとき
- 無認可保育園は除く
-
育児休業を取得している者が、下記のいずれかに該当したとき
- 死亡したとき
- ケガや病気その他の理由で養育することが困難な状態になったとき
- 離婚やその他の事情により、配偶者が子どもと同居しないことになったとき
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定、または産後8週間を経過していないとき
子どもが1歳6カ月になる前日まで延長ができます。もし子どもが1歳6カ月になっても状況が変わらないのであれば、最長で2歳まで再延長が可能です。
ただし、再延長はあくまでも例外的な措置のため、子どもが1歳の段階で2歳までの延長申請はできません。
育児休業給付金の延長で必要な書類
育児休業給付金の延長で必要な書類は育児休業給付金支給申請書に加えて、以下の書類が必要です。必要書類は延長する事由によって異なるため、前述した「育児休業給付金が延長できる条件」と照らし合わせて準備してください。
- 市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類(延長事由が1.に該当する場合)
- 世帯全員について記載された住民票の写しおよび母子健康手帳(延長事由が2.の(1)および(3)に該当する場合)
- 保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等(延長事由が2.の(2)に該当する場合)
- 母子健康手帳(延長事由が2.の(4)に該当する場合)
育児休業給付金の延長の申請先
育児休業給付金の延長の申請先は、初回の申請と同様にハローワークです。基本的には勤務先に提出してもらいます。
育休が終了する2週間前までに遅滞なく提出してください。
育児休業給付金以外で出産・子育てに利用できる制度
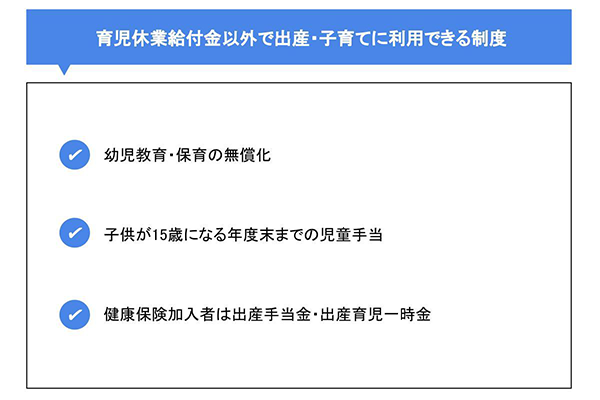
育児休業給付金が支給されることになっても、出産前と比較すると収入減は避けられません。しかし、育児休業給付金以外にも出産や子育てに利用できる制度があります。
制度によっては利用に条件がありますが、家庭にかかる負担を軽減してくれるものばかりです。ここでは3つ紹介します。
幼児教育・保育の無償化
幼児教育や保育の負担軽減を図る少子化対策を目的に、2019年10月より実施されています。無償化の対象は幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3歳~5歳児クラスの子どもや住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスまでの子どもです。
対象者や利用料については以下のとおりです。
- 幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3歳~5歳児クラスの子ども
- 住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスまでの子ども
満3歳になった後の4月1日から小学校に入学するまでの3年間が無償になります。幼稚園の月額上限は25,700円に設定されており、入園する時期に合わせて満3歳から無償化の対象です。
送迎費や食材費などは従来通り保護者の負担になりますが、年収360万円未満の世帯の子どもと、年収に関わらず第3子以降の子どもについては副食費がかかりません。
また、子どもが2人以上いる世帯の金銭的な負担を減らすため、保育所などを利用する年長の子どもを第1子として、0歳~2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料としています。
施設の利用については住んでいる市町村から認定を受けなければなりません。認定には1号~3号まであり、利用できる施設が異なります。利用できる施設は以下のとおりです。
- 1号認定:幼稚園、認定こども園
- 2号認定:保育所、認定こども園
- 3号認定:保育所、認定こども園、地域型保育
利用手続きは認定区分によって申請者が異なります。1号認定は施設経由、2・3号認定は市町村へ直接申請します。
子どもが15歳になる年の年度末までの児童手当
児童手当の支給対象者は中学校卒業までの児童を養育している家庭です。児童手当の支給額は子どもの年齢や何人目の子どもかで変わります。
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳以上~小学生:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:子どもの数に限らず10,000円
支給時期は原則6月、10月、2月の年3回です。
健康保険加入者は出産手当金・出産育児一時金
健康保険に加入している方は、出産手当金や出産育児一時金が支給されます。
| 出産手当金 | 出産育児一時金 | |
|---|---|---|
| 支給対象者 | 産前42日~出産後56日までの期間に会社を休んだ健康保険加入者 | 健康保険の被保険者、または被扶養者で妊娠4カ月以上で出産した方 |
| 支給額 | 標準報酬日額の3分の2 | 子ども1人につき42万円 |
| 手続き | 会社または協会けんぽに申請書を提出する | 加入している健康保険組合や国民健康保険、医療機関(直接支払制度利用時) |
出産手当金は支給期間が長く、収入が減ってしまった家計の大きな助けになるでしょう。支給額は標準報酬日額の3分の2です。標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1として計算され、10円未満は四捨五入されます。
例えば標準報酬月額が20万円の方だと、標準報酬日額は200,000円÷30日=で6,666円です。10円未満は四捨五入されるので6,670円になります。支給額はこの金額の3分の2なので、4,447円と計算できます。
出産一時金は子ども1人につき42万円です。もし死産してしまった場合でも妊娠4カ月以上経過していれば、39万円が受け取れます。
育児休業給付金の気になる疑問

ここまでは育児休業給付金について解説しました。そこでいくつかの気になる疑問についてピックアップしたので、紹介します。
2人目でも育児休業給付金はもらえるか
育休中に2人目を妊娠した場合も、育児休業給付金の給付対象になります。
ただし、育児休業給付金を受け取る条件の「育児休業を開始した日から2年間、就業日数が11日以上の月が12カ月以上あること」を満たさなければなりません。もし、12カ月に満たなくても、保育所に入園できなかったり、本人が病気になったりとやむを得ない理由がある場合は、算定期間が2年間延長され、育休開始前の4年間で判定されます。
また1人目の育児休業給付金の期間内でも、2人目の出産手当金を受け取れます。忘れずに申請してください。
育児休業中に退職したらどうなるのか
育児休業給付金は復職する予定がある従業員に支給する給付金です。そのため、退職した場合は育児休業給付金の給付対象外になります。ただし、退職日を含む支給単位期間の1つ前の支給単位期間までは支給されます。
また、これまで支給された育児休業給付金の返金をする必要はありません。
まとめ

育児給付支援金は育児休業を取得する被保険者が受けとれる給付金です。育児休暇を取得してから、原則として子どもが1歳になるまで受け取れます。
育児給付支援金を受け取るには雇用保険の被保険者であることや、育児休業を開始した日から2年間、就業日数が11日以上の月が12カ月以上あることなどの条件を満たす必要があります。
申請には各種書類が必要で、初回の給付には4〜5カ月ほど時間がかかる場合も。妊娠が判明したら予定を立てて育児休業給付金を申請してください。
(2022年9月9日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以 上