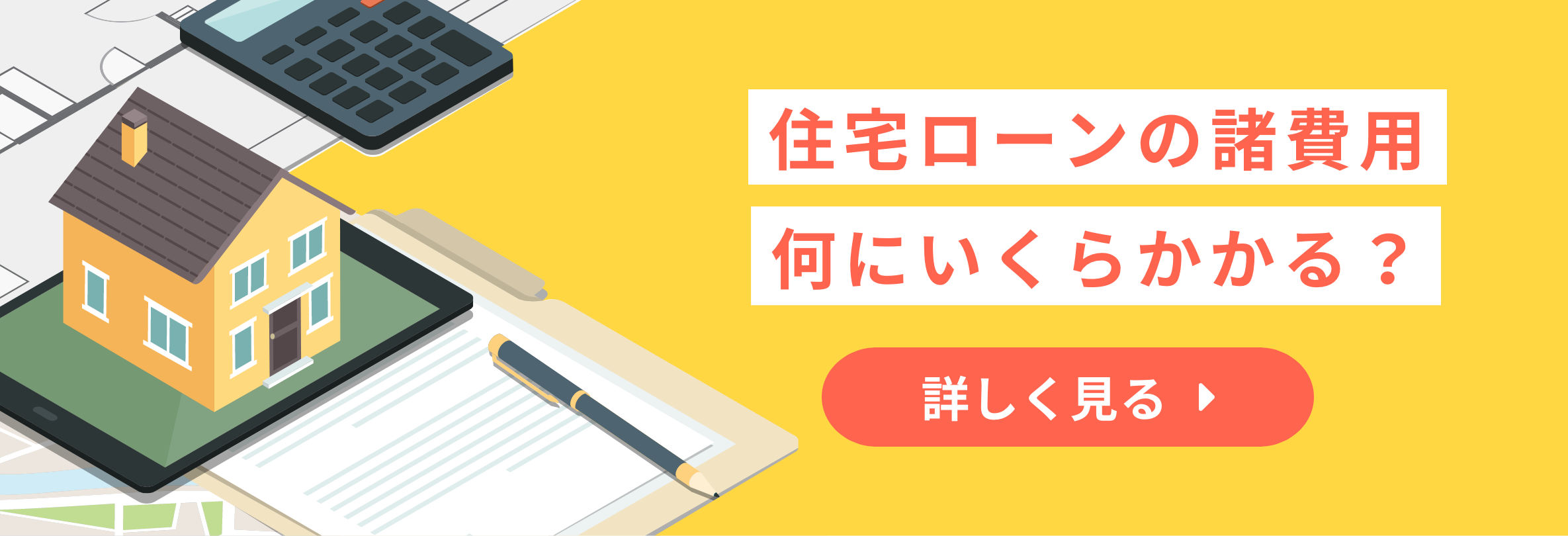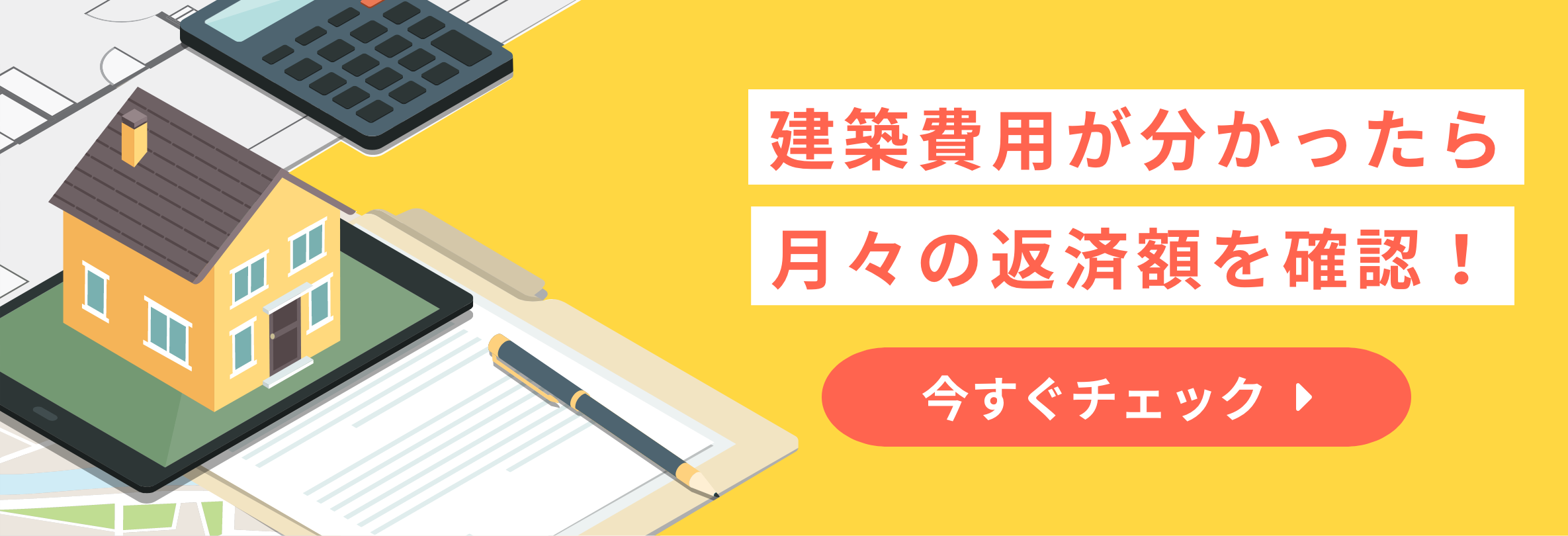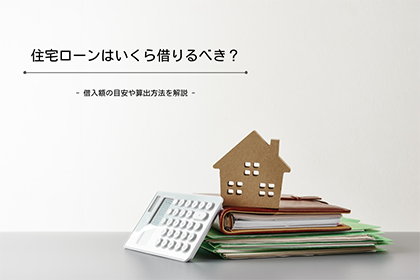【地域別】一軒家を建てる費用はいくら?土地あり/なしの相場や注文住宅の価格帯の違い、費用内訳を解説
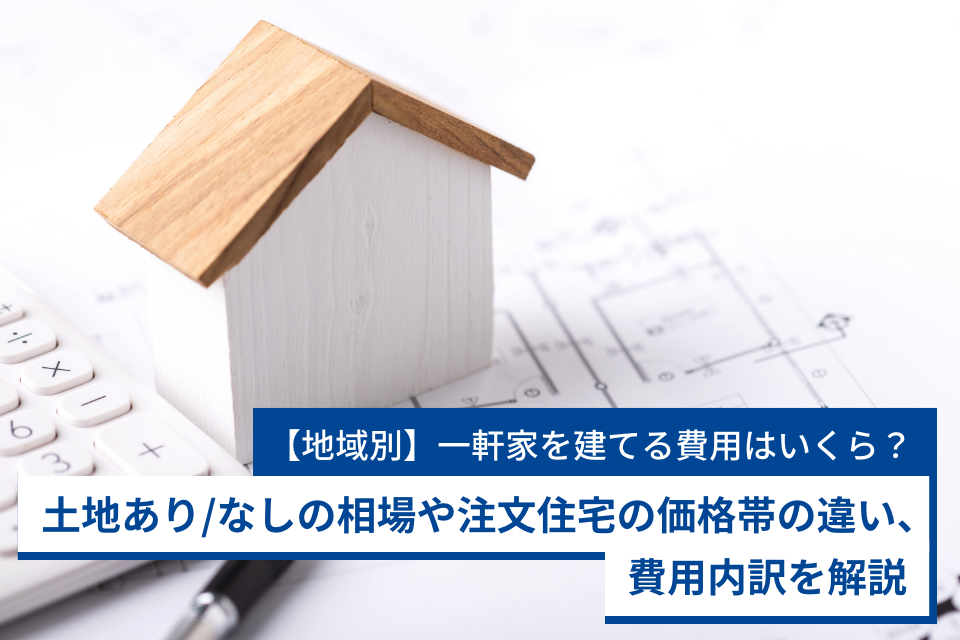
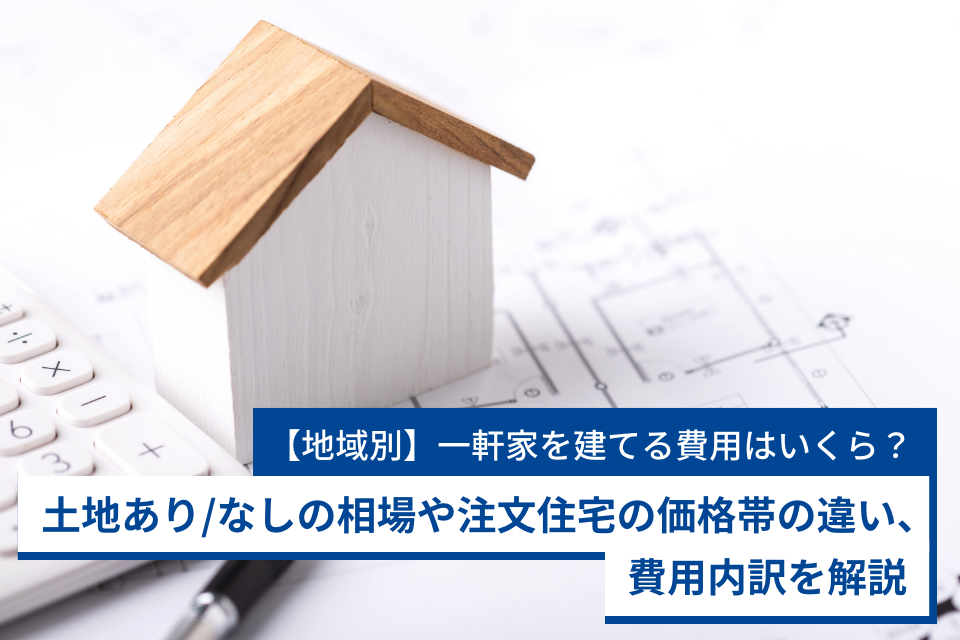
「なるべく安く家を建てたい」「一軒家購入で必要な費用を知りたい」「すでに土地はあるので、建築費用がどの程度かかるのかを知りたい」
家を建てる際、初めに考えるのがお金についてではないでしょうか。地域や仕様によってかかる費用は異なりますが、なるべく希望に合った家を建てたいと考えるでしょう。
今回は、家を建てるためにかかる費用について詳しく解説します。土地の有無、地域ごとの価格の違いについても確認していきましょう。
家はいくらで建てられる?家を建てるのにかかる費用の内訳、土地あり/なしの値段相場を解説
家を建てたい方が最も気になるのは、どのようにして家を建てるのか、および建てるのにかかる費用についてではないでしょうか。
家ができるまでの流れ
家ができるまでの流れを簡単にご紹介します。


STEP 01 建築会社選び
まずは、家を建ててくれる住宅会社を探しましょう。カタログやインターネットで探すだけでなく、時間が許す限り、モデルルームや住宅展示場に出向いて実物を確認してください。各社の特徴や得意分野を把握できます。
また、以下の点もチェックしましょう。
- 土地を持っていない場合は、土地探しもサポートしてくれるか
- 着工後の変更にどこまで対応してくれるか
- 保証、アフターフォローはあるか
- 営業担当者は信用できそうか
- 建築を請け負う会社は信用できそうか
STEP 02 土地探し(土地を持っていない場合)
土地がない場合は土地を探します。候補が見つかったら現地まで行き、日当たりや利便性、周囲の環境を確認しましょう。一般的には土地購入までに数カ月程度を要します。住宅会社によっては、土地を探してもらえる場合もあります。
STEP 03 見積もりとプランニング
土地探しと並行して、希望の間取りに沿って見積もりを作成してもらいましょう。必要な部屋数や希望のデザインなどをきちんと伝えてください。複数の住宅会社に見積もりを出してもらい比較検討することをお勧めします。
STEP 04 契約締結
見積もりの確認や打ち合わせを行い、詳細が決定したら工事請負契約締結に進みます。契約締結後、変更が生じる場合は、変更契約が必要になりますので、納得したうえで契約を結びましょう。
STEP 05 工事着工
工事請負契約を締結後、工事着工です。着工から工事完了までは半年ほどかかると見ておきましょう。
STEP 06 工事完了と引渡し
工事が完了したら、契約どおりに工事が行われたかを確認し、引渡しになります。また、工事完了時には、建築基準法に沿って建てられているかの確認も行われ、自治体の建築主事、もしくは指定の民間確認検査機関が「検査済証」を発行します。検査済証は引渡し時に受け取ります。
家を建てる時にかかる費用の内訳
家を建てる場合、次のような費用がかかります。
- 土地購入費用
土地を持っていない場合、土地を購入する必要があります。
- 本体工事費
建物本体にかかる工事です。
なお、家をつくる際によく聞かれる「建築坪単価」とは、本体工事費を延床面積の坪数で割った金額のことです。
- その他工事費
「外構工事」などは本体工事費に含まれず、その他工事費になります。
- その他経費
「登記費用」「保険料・保証料」「住宅会社に支払う手数料」なども必要です。
【地域別】家を建てるのにかかる費用を紹介
住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査」から、注文住宅を建てる費用を土地あり、なし別に確認してみましょう。
【土地ありの場合】
土地がある場合の家を建てる費用は以下のとおりです。
| 地域 | 建築費 |
|---|---|
| 全国平均 | 3,861.3万円 |
| 三大都市圏 | 4,110.7万円 |
| 首都圏 | 4,191.6万円 |
| 近畿圏 | 4,142.1万円 |
| 東海圏 | 3,894.5万円 |
| その他地域 | 3,623.2万円 |
| 茨城県 | 3,580.3万円 |
出典:住宅金融支援機構「フラット35利用者調査 2023年度集計表」を元に表を作成
【土地なしの場合】
土地がない場合、土地購入費も必要です。各費用は以下のとおりとなっています。
| 地域 | 建築費 | 土地購入費 |
|---|---|---|
| 全国平均 | 3,405.8万円 | 1,497.6万円 |
| 三大都市圏 | 3,423.0万円 | 1,955.7万円 |
| 首都圏 | 3,402.3万円 | 2,277.3万円 |
| 近畿圏 | 3,414.5万円 | 1,850.8万円 |
| 東海圏 | 3,491.1万円 | 1,319.4万円 |
| その他地域 | 3,384.0万円 | 915.3万円 |
| 茨城県 | 3,357.7万円 | 748.4万円 |
出典:住宅金融支援機構「フラット35利用者調査 2023年度集計表」を元に表を作成
土地がない場合、土地購入費も支払う必要があるためなのか、土地ありの場合よりも建築費が低めになっているようです。
ここまでのまとめ
家を建てる期間は、土地がない場合で約1年〜1年半、土地がある場合で約8カ月〜1年2カ月ほど。
建築会社は、モデルルームを確認したのち保証内容やアフターフォロー、実績を考慮して選ぶと良い。
家を建てる際には「土地購入費」「本体工事費」「その他工事費」「その他経費」がかかる。
土地がある場合の建築費の全国平均は「3,861.3万円」
土地がない場合は建築費に「土地購入費」が加わり、全国平均は「4,903.4万円」
建売住宅と注文住宅の違いとメリット・デメリット
家を建てる際、建売住宅と注文住宅で迷われている方も多いのではないでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを確認してみましょう。
建売住宅とは?
建売住宅は、土地・建物が一緒に販売されている住宅のことです。建売住宅のメリットは次のとおりです。
建売住宅のメリット
-
内覧したうえで購入ができる
すでに完成している場合は内覧したうえで購入できます。住んだ時のイメージがしやすいというメリットがあります。
-
間取り等を考える必要がない
注文住宅とは違い、一から間取りを考える必要がありません。
-
価格帯が低め
注文住宅よりも価格が低く設定されています。
-
諸手続きに時間を取られない
建売住宅は価格もはっきりしているため、住宅ローン審査に申し込みしやすいというメリットがあります。また、購入契約から引越しまでの期間も短くて済みます。
続いて建売住宅のデメリットも確認しておきましょう。
建売住宅のデメリット
-
自分で間取りや設備を選べない
すでに完成している、もしくは建設中のため、自分で間取りや設備を選べません。
-
どのように建築されているかが分かりにくい
建売住宅の場合、建築過程の確認ができません。どのような素材や土台を使っているかが分かりにくい点はデメリットといえるでしょう。


注文住宅とは?
注文住宅とは、自分で間取りや設備を指定して建ててもらう住宅のことです。
注文住宅の最大のメリットは自由度が高い点です。詳しく見ていきましょう。
注文住宅のメリット
-
間取りや設備を自分で選べる
自分たちが暮らしやすいように間取りや設備を選べます。
-
木造・鉄筋コンクリートなど、工法が選べる
希望に合わせて、木造建築、鉄筋コンクリートなど工法が選べます。
-
家が建つ過程を見ることができる
注文住宅の場合、施工の各段階を確認できるため、建築の進捗や品質を把握しやすくなります。万が一、気になる点があれば、早めに修正を依頼できるのもメリットです。
-
仕様を確認することができる
使用する建材や設備の仕様、空間の広さなどを事前にチェックできるため、仕上がりのイメージと実際のギャップを減らすことができ、納得したうえで家づくりを進められます。
注文住宅は自由度が高い分、デメリットが何点かあります。
注文住宅のデメリット
-
価格帯が高め
建売住宅と比べ、価格が高いというデメリットがあります。
-
土地を持っていない場合、土地を探す必要がある
希望するエリアに土地が見つからない可能性もあります。
-
完成・引渡しまでに時間が必要
工事契約後、完成・引渡しまでに1年以上かかる場合もあります。


【予算別】建てられる家の仕様の違いを解説!
家を建てる際に、予算に応じてどのような家が建てられるのか気になる方も多いでしょう。そこで、予算別に建てられる家の仕様をご紹介しますので参考にしてください。なお、ここでの予算は建築費のみの場合です。
1,000万円台で建てられる家
1,000万円台の家は、多くの場合『プランが決まっている規格住宅』の中から、自分にあったプランを選びます。
規格住宅は、住宅のプロが「誰でも住みやすい住宅」を既製品として提供しているため間取りやデザインの自由度は低いものの、失敗しにくい設計が施されます。オプションを追加して費用をかければ自分好みの設備を導入することも可能です。


2,000万円台で建てられる家
予算2,000万円台の場合、1,000万円台に比べて余裕はありますが、全てにお金をかけられるわけではありません。「最新設備でなくても良いから間取りだけは希望どおりにしたい」「内装はシンプルにして水回りだけはお金をかけたい」など、どこにお金をかけるかを明確にしておくことが重要です。


3,000万円台で建てられる家
全国平均や茨城県の平均建築費用が3,000万円台であることから、このくらいの予算があれば、ある程度希望どおりの家が建てられるでしょう。
ただし、「贅沢なつくりの家」は難しいかもしれません。コストを抑える部分をきちんと決めておくことが大切です。


5,000万円台で建てられる家
この予算であれば、こだわりの家を建てることができます。間取りや内装だけでなく、外壁・屋根などにもこだわってつくることができるでしょう。また、広い家や部屋数が多い家にすることもでき、3階建てや完全分離型二世帯住宅も実現できます。


【留意点】
建築コストなど物価水準によっては、上記の例とは異なることがありますので、ご留意ください。
家を建てる費用を抑えるためにできること
予算別に建てられる家についてご紹介しましたが「なるべく費用を抑えたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。費用を抑えるためにできることをご紹介します。
複数の住宅会社を検討する
初めから1つの住宅会社に絞るのではなく、複数の会社を比較検討してください。予算や希望の間取りなどを伝え、見積もりを取って比べてみましょう。
条件を少なくする
価格を抑えるためには条件を少なくすることも重要です。具体的には「部屋数を減らす」「内装・設備にこだわらない」「外壁・屋根の素材にこだわらない」などです。
複雑なつくりの家にしない
間取りや内装をシンプルにすると価格を抑えられます。また、「吹き抜け」や「ビルトインガレージ」など、複雑なつくりを希望しないようにしましょう。
設備等の性能を見直す
最新の設備を入れるとどうしても価格が高くなります。価格を抑えたいのであれば、ランクを下げた設備を選びましょう。もしくは「浴室だけは最新型でその他の設備は低めのランクにする」など、お金をかける場所を限定するようにしましょう。
減税や補助を利用する
住宅関連の減税や補助は忘れず利用しましょう。2025年2月現在、以下のような減税・補助があります。
| 種類 | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン減税 |
住宅および敷地となる土地購入に住宅ローンを利用した場合、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除される。 その他の適用条件など住宅ローン減税の詳細は国税庁HP(https://www.nta.go.jp/)を参照してください。 |
||||
| 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 |
合計所得金額2,000万円以下の人が、父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築・取得・増改築のための資金贈与を受けた場合、一定の金額について贈与税が非課税となる。 (適用期限:2026年12月31日までに贈与を受けた場合) 【限度額】
|
||||
| 子育てグリーン住宅支援事業 |
以下に当てはまる世帯が、GX志向住宅、長期優良住宅またはZEH水準住宅を新築する場合、1戸あたり40~160万円が補助される。 ※1:2024年11月22日以降に工事着手したものに限定します。 ※2:本補助金を受けるためには申請が必要となります。 ※3:詳細は国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/index.html)を参照してください。
|
家を建てる際に注意したいこと
最後に家を建てる際に注意したい点を解説します。
「地目」を確認する
地目とは、不動産登記法により定められた土地の用途のことです。「田」「畑」「宅地」「山林」「原野」など、23種類あります。
どの地目であっても家は建てられますが、宅地以外に家を建てた場合は地目を「宅地」に変更してください。「田」「畑」を農地転用して宅地に変更する場合には、農業委員会の証明書が必要です。手続きが難しい場合は行政書士等に相談しましょう。
減税や補助を忘れずに活用する
家を建てる際の負担を抑えるためにも、先ほど紹介した「住宅ローン減税」などの減税や補助を忘れずに活用してください。
住宅ローンの諸費用もチェックする
家を建てる際に、多くの方が住宅ローンを利用しますが、住宅ローン契約を利用して購入した場合、税金やその他費用も含めて物件価格の5~10%程度の諸費用がかかります。これらの負担についても把握しておきましょう。
![]() 住宅ローン関連費用
住宅ローン関連費用
- 銀行事務取扱手数料
- 印紙税
- 登録免許税
- 登記手数料
- 火災保険料
- 保証料
![]() 税金関連
税金関連
- 不動産取得税
- 固定資産税
![]() その他
その他
- 不動産仲介手数料(不動産会社を通じて土地を購入した場合)


家を建てる際の費用をきちんと把握し、後悔のないマイホーム選びを
例えば茨城県の場合、一戸建ての平均建築費用は土地ありで3,580.3万円、土地なしで3,357.7万円です。茨城県に限らず、全国的にも予算が3,000万円台であれば、ある程度は希望どおりの家が建てられるはずです。
ただし、予算1,000万円台や2,000万円台などの場合、費用を抑えたいのであれば、内装をシンプルにする、外壁にこだわらないなど、妥協も必要になります。家族でよく話し合ってみましょう。
家を建てる際は、住宅ローン関連費用や税金など、家の価格以外にも多くの諸費用がかかります。なるべく負担を減らすためにも、減税や補助も活用しましょう。
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。