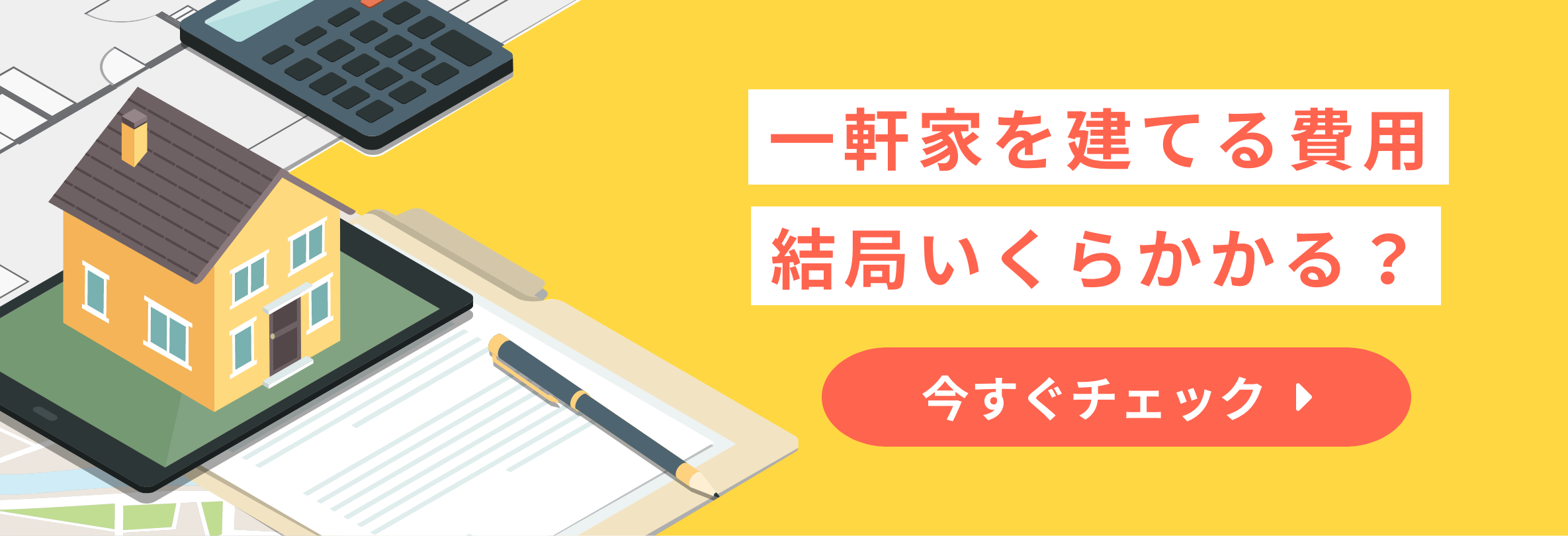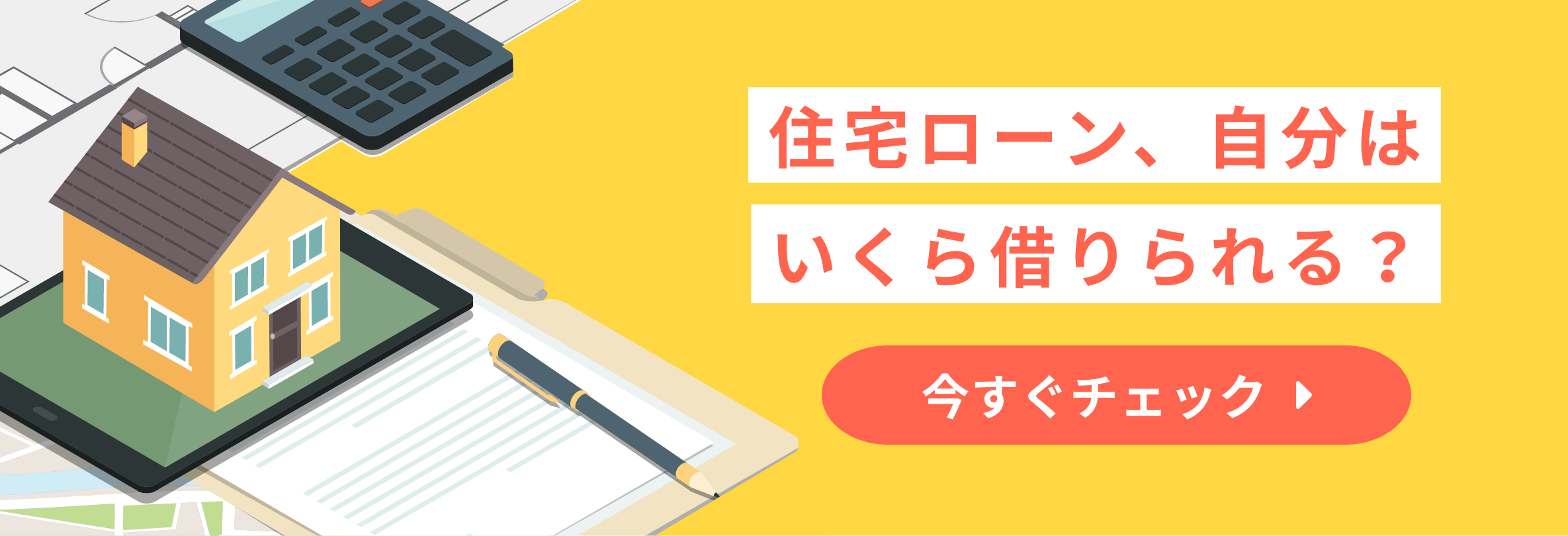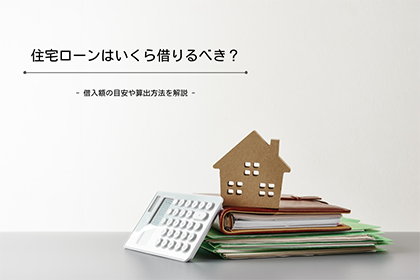平屋のメリット・デメリットは?
人気の理由と向いている人の特徴


1階建てで、シンプルな暮らしができる「平屋」。
生活・家事動線が良く、バリアフリーな暮らしができることから、近年「平屋」(1階建て)・「半平屋」(1.5階建て)ブームが巻き起こっています。
ただし、平屋・半平屋ならではの注意点もあるため、メリット・デメリットを踏まえて、自分たちの理想の暮らしに合っているかを見極めることが大切です。
そこで本記事では、平屋と半平屋のメリットとデメリット、平屋・半平屋暮らしが向いている人を解説します。これから家づくりを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
平屋建てに住む5つのメリット!注文住宅の平屋や半平屋が人気の理由とは?
「広い土地があれば平屋を建てたい」という人は以前から多くいましたが、近年は実際に平屋を選ぶ人が増えています。『令和5年住宅・土地統計調査』によると、2023年(令和5年)に茨城県で建てられた新築住宅のうち、約20%が平屋。つまり新築住宅のうち、5軒に1軒は平屋という計算になります。
なぜ今、平屋が人気を集めているのか。その理由を、平屋や半平屋のメリットとともに紹介します。
参考:総務省統計局『住宅・土地統計調査 令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計』
動線がシンプルで暮らしやすい
平屋の最大の魅力は、生活動線がシンプルなことです。
階段の上り下りがなく生活空間がすべて同じフロアにあるので、家の中の移動距離が短く、無駄な動きがありません。さらにキッチン、リビング、寝室、浴室といった主要な生活空間を一続きにすれば、家事の効率がぐっと良くなります。
料理をしながら洗濯機を回したり、子どもの様子を見ながら掃除をしたりと、“ながら家事”もしやすく、共働きなどで早朝や夕方に家事を済ませなければならない家庭でも、家事をしながら家族とのコミュニケーションを取りやすくなります。
「収納量が心配」「家族との距離感も大事にしたい」といった場合には、ロフトや半平屋という選択肢もあります。
半平屋とは、平屋をベースにしつつ一部に2階を設けた間取りで、平屋の快適さと2階建ての機能性の両方を兼ね備えたスタイルです。高さ1.4m以下のロフトであれば床面積に含まれず、収納スペースとして活用できます。半平屋ならば、2階部分に個室や趣味の部屋を設けることも可能です。
ロフトや半平屋を採用すればワンフロアの空間に視覚的な変化が生まれるため、デザイン性も高めることができます。
バリアフリーな暮らしができる
平屋は上下の移動がないため、段差のない完全バリアフリーの住宅も実現できます。高齢者や小さなお子さんのいる家庭、また将来的に介護を視野に入れている方にとっても、安心して暮らせる住まいになるでしょう。
自分たちのライフステージが変わっても、長く快適に暮らせる住環境を維持し続けられるのは、平屋ならではのメリットと言えます。
光熱費を抑えられる
平屋は冷暖房を効かせる範囲が2階建てよりも狭いので、高気密高断熱住宅であればエアコン1台で居住空間ほぼ全体の温度管理ができます。
家庭のエネルギー消費の50%以上は電気で、さらに暖房によるエネルギー消費量は20%程度を占めているため、エアコンの稼働率を下げれば消費電力を大きく抑えられます。快適な温度を保ちながらも光熱費を削減できる点も、平屋のメリットと言える部分です。
参考:省エネポータルサイト『省エネって何?』
参考:環境省『暖房について』
耐震性・耐風性を高めやすい
平屋はシンプルな構造で耐震設計がしやすく、住宅の耐震性を高めやすい点がメリットです。2階建てに比べて建物にかかる重量が少ないため、揺れによる負担も小さくなります。
また、建物の重心が低く、風を受ける面積が小さいことから耐風性にも優れています。
外壁や屋根のメンテナンスがしやすい
2階建ての場合、外壁や屋根のメンテナンス時には足場を設けるため、40坪の2階建て住宅なら20万円前後の足場代が必要となることが多いです。
一方で平屋は建物の高さが低いため、外壁や屋根のメンテナンスの際に足場を設けずに作業できることも。足場代分のメンテナンス費を抑えられる点がメリットです。
ただし、天井が高い平屋や半平屋では、2階建てと同じように足場が必要になるので、メンテナンス費用が気になる方は、プランニング時に建物の高さを確認することをおススメします。


平屋や半平屋に住む4つのデメリットと対策
平屋や半平屋にはさまざまなメリットがある一方で、注意しておきたい点もあります。ここでは主な4つのデメリットと、それぞれの対策方法について解説します。
広い土地が必要になる
平屋を建てるためには、2階建て住宅に比べて広い土地が必要です。
コンパクトな平屋ならば50坪前後の土地でも建てられますが、庭や駐車場の確保を考えると60坪以上の広さが理想的です。2階建て住宅よりも、広い土地を購入することになるでしょう。
「広い土地が必要になる」と聞くと購入費用が心配になるかもしれませんが、水戸市の2025年(令和7年)における住宅地の平均公示地価は、130,757円/坪(39,554円/㎡)。平均値から考えると、60坪の土地なら諸費用を含めても800万円前後で購入できる計算です。他の関東圏の地域と比べると、平屋を実現しやすい地域と言えます。
参考:地価公示・地価調査(基準地価)マップ『茨城県水戸市 地価公示 マップ [2025年]』
水害リスクが高い土地だと2階に避難できない
平屋は2階がないため、万が一床上浸水が発生した場合には自宅内での避難が困難になります。
そのため平屋を建てるのなら、水害リスクをしっかりと確認したうえで土地選びを行う必要があります。国土交通省が提供する『重ねるハザードマップ』を確認しながら、候補地を絞ってみてください。
もし、水害リスクがある土地に平屋を建てるのなら、予想浸水深に合わせて基礎高を上げる、盛り土をする、半平屋にして避難場所を確保するなど、プランニングでの工夫が必要です。
参考:国土交通省『重ねるハザードマップ』
土地の条件によっては採光や通風が難しい
建物の高さが低い平屋は、周囲の建物や環境の影響を受けやすくなります。特に住宅密集地や都市部の狭小地などでは、日当たりや風通しが悪くなることも。
対策としては、天窓やハイサイドライト(※)の設置、中庭を取り入れたロの字型やコの字型の設計、吹き抜けの活用などで改善が可能です。しかし、建物を複雑な形状にするとその分建築費用も高くなるため、延べ床面積を小さくするなど、予算に合わせた対応が必要です。
※ハイサイドライトとは、壁の高い位置、主に天井近くに設けられる横長やスリット状の窓を指し、「高窓」とも呼ばれます。 主な目的は採光と通風で、外からの視線を避けつつ、部屋の奥まで効率的に自然光を取り入れたり、換気を促進したりするのに役立ちます。
建築費用の坪単価が2階建てよりも高い
平屋は屋根と基礎の面積が広くなるため、同じ延べ床面積であっても2階建てよりも坪単価が高くなる傾向にあります。
これが、「平屋は割高」だと言われる理由です。
費用を予算内で収めるためには、コンパクトな平屋にして2階建てよりも延べ床面積を少なくする、シンプルな形状にするなど、希望の取捨選択が求められます。
また、限られた面積でいかに空間を有効活用できるのか、提案力も求められるため、住宅会社選びも重要です。


平屋や半平屋の家が向いている人の特徴
住宅購入において大切なのは「自分にとって最適な住まいは何か」を見極めることです。ここでは、特に平屋や半平屋の家が向いている人の特徴をご紹介します。
バリアフリー環境が欲しい人
なんといっても平屋は階段がなくワンフロアで暮らせるため、無駄のないシンプルな生活空間を実現できる間取りです。
前述のように動線が短くシンプルなので、家の中の移動がスムーズ。
そのため、高齢者や小さなお子さんがいる家庭、介護が必要な家族がいるなどの理由でバリアフリー環境を求める人にはうってつけと言えるでしょう。
家事効率を重視したい人
平屋は家の中の移動距離が短くなるため、家事を効率良く進めることができます。さらに『回遊動線』を取り入れれば、“ながら家事”はもちろん、家の中を動き回りながら家事を進められるので、家事効率が格段にUP。
ファミリークローゼットを設けてランドリースペースとつなげれば、「洗濯、干す、たたむ、収納」までがワンストップで行えます。
タイパ(タイムパフォーマンス)を重視したい人にとっても、平屋は最適の選択肢です。
家族とのコミュニケーションを大切にしたい人
ワンフロアで家族全員が生活する平屋は、家族との距離が近く、コミュニケーションの取りやすさが魅力。そのため「家族で過ごす時間を増やしたい」「それぞれのライフスタイルが変わっても、家族の気配を感じたい」など、家族とのつながりを大切にしたい方におススメです。
ただし、プライベートな空間の確保も重要です。お子さんの思春期や自分たちにストレスがかかっているときに、1人になれる空間があるほうが良い場合もあります。
家族間でのプライバシー面に不安があるときには、半平屋にするのもひとつ。2階部分に1人で過ごせる書斎や趣味の部屋を設けるなど、希望を叶えつつも不安要素を解消できるプランを考えてみてください。


平屋や半平屋のメリット・デメリットをしっかりと理解して、理想の住まいづくりを!
動線がシンプルで暮らしやすいことや家族でのコミュニケーションを取りやすいことが、平屋や半平屋が人気を集めている理由だと分かりました。その一方で土地の広さや建築費用、災害時の対応など注意すべき点もあるため、誰しもに向いているわけではありません。平屋や半平屋が本当に自分たちの暮らしに合っているか、家族でじっくり話し合うことが大切です。
家づくりの資金面での悩みは、ぜひ常陽銀行にご相談ください。
借入額のシミュレーション、無理のない返済計画のご提案など、住宅ローンに関するご相談を承っております。
理想の住まいと安心の暮らしを両立するために、住宅ローン選びも含めて、納得の家づくりを始めましょう。
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。