家賃はいくらに抑えるべき?収入別目安や家賃を安く抑えるコツを紹介

家賃の目安はどのくらい?
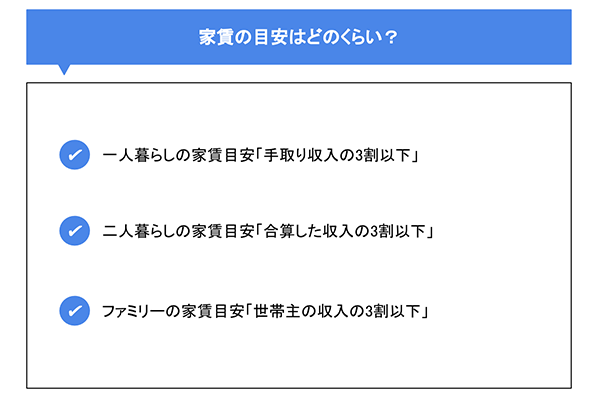
生活費の中でも大きな支出となる家賃。賃貸で住む家を探すとき、家賃が決め手となるケースは多いようです。一方で、自分の収入に対して家賃が妥当な金額なのかよく分からない、という話もよく聞きます。家計に負担をかけず、無理なく払えて、さらに収入に見合った家賃の目安とは一体どのくらいなのでしょうか。
年収や世帯人数によっても異なりますが、家賃の目安としては、手取り収入の3割以内の金額とするのが一般的です。手取り収入とは、給与などの収入から各種保険や税金などが差し引かれて手元に入ってくるお金のこと。家賃が手取り収入の3割以上になると、その他の支出を極端に節約しなければ家計がまわらなくなる可能性が高くなります。
この記事では、収入や世帯人数別の家賃の目安のほか、予算をオーバーしてしまうときに家賃を安く抑える方法を紹介します。
一人暮らしの家賃目安「手取り収入の3割以下」
一人暮らしを始める際、気になるのが家賃の目安。特に、これから一人暮らしを始める方は、家賃をいくらくらいに抑えると無理のない生活ができるか気になるところではないでしょうか。初めての一人暮らしでは、自分にとっての最適な家賃はなかなか分からないものです。
一人暮らしの場合、家賃の目安は手取り収入の3割以下が理想です。しかし、全体的に家賃の相場が高い都心など、場所によってはなかなか条件に合う物件が見つからず、予算をオーバーしてしまうこともあります。そのような場合は食費や光熱費、交際費など、その他の支出を抑えることで、月々の支出のやりくりをしていく必要があります。
二人暮らしの家賃目安「合算した収入の3割以下」
友人とのルームシェアや同棲、夫婦での二人暮らしの場合は、どちらか一方にしか収入がないときは一人暮らしのときと同様、手取り収入の3割以下が家賃の目安となります。共働きでダブルインカムの場合は、2人の手取り収入を合算した金額の3割以下で考えてみると良いでしょう。家賃を2人で折半した場合、1人のときよりも家賃にまわせるお金が増えるので、一人暮らしではなかなか住めないような条件の良い物件にも住むことができるようになります。
ファミリーの家賃目安「世帯主の収入の3割以下」
家族で住む家の場合は、何かあったときに困らないよう、世帯主の収入の3割以下を家賃の目安にするのがおススメです。
二人暮らしの場合同様、夫と妻の手取り収入を合算した金額の3割以下で考えても問題はないのですが、出産や育児など何らかの理由で妻(もしくは夫)が働けなくなったときや、突然収入が減るようなことがあったとき、家賃が家計を圧迫することになります。しかし、最初から世帯主の収入の3割以下の家賃にしておけば、何かしらの変化があったときも家賃の支払いが大きな負担にならないので安心です。
手取り収入別の家賃目安

| 一カ月の手取り収入 | 家賃目安 |
|---|---|
| 15万円 | 45,000円以内 |
| 20万円 | 60,000円以内 |
| 25万円 | 75,000円以内 |
| 30万円 | 90,000円以内 |
| 35万円 | 105,000円以内 |
家賃目安を手取り収入の3割以下とした場合
上記は手取り収入別に家賃の目安をまとめたものです。収入が20万円の場合は6万円、30万円の場合は9万円が家賃の目安となります。賃貸住宅を探す地域によっては目安となる家賃の物件が見つからないこともあるかもしれません。しかし、この金額はあくまで目安です。家賃が手取り収入の3割以上になってしまう場合は、家賃が家計を圧迫しないよう、生活費の確認と見直しをしてみると良いでしょう。
家賃は収入から生活費を引いて余裕がある額に抑える

収入ごとに家賃の目安はあるものの、収入やライフスタイルの違いで、家賃をいくらに抑えるべきかは人によりそれぞれ異なります。これから新しい家を探し始める方や、家賃を見直そうと思っている方は、自分の収入と生活費のバランスで家賃を検討してみると良いでしょう。理想は、手取り収入から生活費を引き、さらに家賃を引いても余裕がある状態。平均より出費が多い項目や全体の生活費を把握してから、家賃に充てられる予算を出してみましょう。
生活費の全国平均は?
| 単身者 | 二人以上の世帯 | |
|---|---|---|
| 食料 | 44,209円 | 80,461円 |
| 光熱・水道 | 11,425円 | 21,951円 |
| 家具・家事用品 | 5,482円 | 11,717円 |
| 被服および履物 | 6,147円 | 11,306円 |
| 保健医療 | 7,340円 | 14,010円 |
| 交通 | 4,666円 | 6,101円 |
| 通信 | 6,929円 | 13,599円 |
| 教養娯楽 | 18,719円 | 30,679円 |
| その他 | 26,887円 | 50,843円 |
| 合計 | 131,804円 | 240,667円 |
出典)家計調査 家計収支編 2019年の全国生活費の平均 品目分類(2020年改定)
上記の表は、総務省統計局による、一人暮らしと2人以上で住んでいる世帯の生活費の全国平均です。1人の場合は約13万円、2人以上の場合は約24万円が生活費の平均金額となります。
この全国平均の生活費を元に、まずは各項目の費用を実際の金額に変更し、生活費が大体いくらくらいになるのか概算してみましょう。そして、収入から概算した生活費を差し引いた金額を算出します。そうすると、家賃をいくらに抑えるべきなのか大体の費用感が分かります。
家賃を安く抑えるコツ
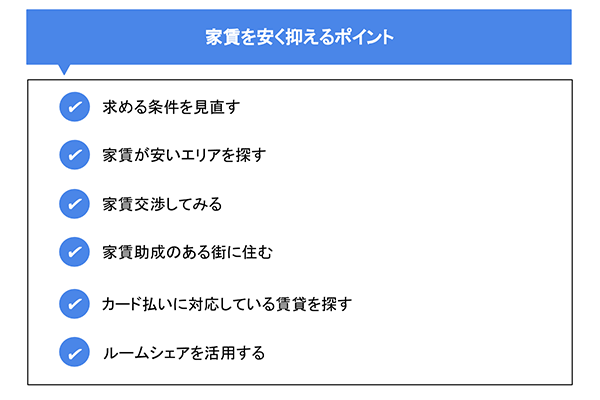
家は生活の基盤となる大切な場所です。家賃を気にせず理想の住まいを選びたいものですが、家賃は毎月の大きな支出でもあるため、「できる限り安く抑えて出費を減らしたい」と思っている方も多いと思います。
実は、家賃を安く抑える方法はいくつかあります。ここでは、家賃を少しでも安く抑えるためにできる6つのことをご紹介します。
求める条件を見直す
デザイナーズマンションなど、人気の物件は総じて家賃が高いもの。家賃が高い家の特徴としては、新築・築浅物件で、部屋が広いなど間取りが良く、設備が充実していることが挙げられます。また、最寄り駅から近く利便性の高い場所や、都心部などの人気エリアも家賃の相場は高くなります。
逆に言えば、これらを条件から外すことで、家賃を安く抑えられる可能性は高くなります。例えば、広い家に住みたい方は、駅や都心部から離れた場所を選ぶことで、家賃を抑えながらも広い家を見つけやすくなるでしょう。家賃を少しでも抑えるために、妥協できる条件がないか再度検討してみましょう。
家賃が安いエリアを探す
都心部や人気のエリア、交通の便が良い立地、コンビニやスーパーなど周囲の環境が充実している地域は、周辺のエリアと比べると家賃が高い傾向にあります。そもそも土地の値段自体が高いエリアは家賃の相場も全体的に高いので、家賃を抑えるなら土地の値段が安いエリアで家を探すのが良いでしょう。
今は、インターネットを使って情報収集ができるので、物件探しには家賃の安い地域を特集している専門サイトを活用するのもおススメです。ネットなら、希望する家賃の住宅も短時間で探すことができます。
家賃交渉してみる
家を契約する際、家賃交渉をすると、家賃を下げてもらえることがあります。必ずしも賃料が下がるわけではありませんが、やってみる価値はあるでしょう。
ポイントは、タイミングと物件の条件です。2月~3月、8月は、引越しが盛んで家賃交渉が成立しづらいため、この時期は避けるのが無難です。また、希望の住宅の家賃が周辺エリアの相場より高かったり、空室期間が長い場合、貸す側は多少家賃が値下がりしても貸したいと思っているケースもあるので、家賃の交渉は成功しやすいかもしれません。
同様に、現在住んでいる賃貸住宅でも、物件が著しく劣化している場合や、近所の環境の変化や悪化、利便性の低下などがあった場合は、契約更新のタイミングで家賃の値下げをしてもらえることがあります。
家賃助成のある街に住む
「家賃助成制度」とは、その地域の定住を目的として、行政が主体となって実施している家賃補助制度のことです。市区町村など自治体の提示した条件に合致すれば、自治体が家賃の一部を負担してくれます。
地域によって家賃助成の条件や内容は異なり、募集は年に数回と多くはないため、応募者も多く、補助制度が必ず受けられるわけではありません。しかし、多くの自治体が家賃助成制度を設けているので、制度のある地域を選んで住むのもひとつの方法です。気になっている地域があれば、制度の詳細や利用条件について一度確認してみると良いでしょう。
カード払いに対応している賃貸を探す
クレジットカード払いに対応している不動産会社の増加に伴い、クレジットカードで家賃を支払うことができる賃貸住宅も増えています。カード払いは、毎月の支払いの手間がなくなり楽になるだけでなく、ポイントやマイルで還元されることが多いというメリットがあります。
還元率はカード会社や利用ステージなどによっても違いますが、クレジットカード払いに対応している賃貸住宅であれば、多くのポイントを貯めることができ、結果的に家賃を安く抑えることができます。家賃のカード払いができない場合も、初期費用はカード払いができるケースもあるので、そのようなときはカードで支払いポイントを貯めるのも良いでしょう。
ルームシェアを活用する
ルームシェアや同棲など2人以上で一緒に住むことでも、経済的な負担を軽くすることができます。家賃を折半することで、一人暮らしの場合よりも家賃を安く抑えることができ、さらに一人暮らしのときには手の届かなかった広い家や人気のエリアなど条件の良い家に住めることもあります。家賃だけでなく、水道光熱費や食費などの一部生活費も安く済むケースが多いようです。
ただし、家賃や生活費の一部が安くなるメリットがあっても、2人以上での共同生活にはデメリットとなることもあります。他人と暮らす場合は事前に様々なルールを作っておくと安心です。
家賃を抑えて将来のために貯蓄しよう!

毎月の支払いが発生する家賃は、必要な費用とはいえ、かなりの額の出費になります。例えば7万5000円と7万円の家賃では、1年で6万円、4年で24万円もの差額が出ます。
高い家賃を出した分だけ条件の良い家に住むことができますが、その出費、本当に必要でしょうか。特に、人生100年時代と言われる今、家賃を抑えて捻出したお金で将来のために備えた方が安心だという見方もできます。家賃を抑えてできたお金で、将来のための貯蓄を始めませんか?
おススメは、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の利用です。通常、株式や投資信託などから得られる配当や譲渡益には所得税や地方税がかかります。ところが、NISAを利用すると新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を非課税にすることができます。また、毎月一定額を購入する「積立投資」は、一度申し込みをすると自動的に積み立てがされるため手間なく資産形成をすることができます。常陽銀行の積立投資信託なら月々1,000円から始めることができるので、まずは少額からスタートしてみるのはいかがでしょうか。
NISAを始めよう!(2024年1月4日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以 上