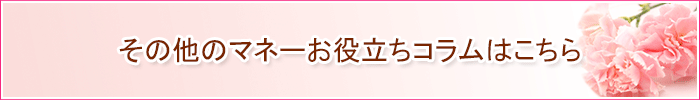親の介護に民間保険は必要?介護保険の制度や受けられるサービスを紹介

「親が寝たきりになって介護施設への入居が必要になった」「認知症が進行して、自宅では介護できなくなった」といった時に活用できるのが介護保険です。介護保険制度は、介護サービスでかかった費用の一部が給付される制度です。しかしさまざまなサービスが受けられる反面、適用範囲が複雑です。そこで今回は、介護保険制度の仕組みや、適用範囲、受けられるサービスなどについて解説します。
親の介護に利用できる介護保険制度とは
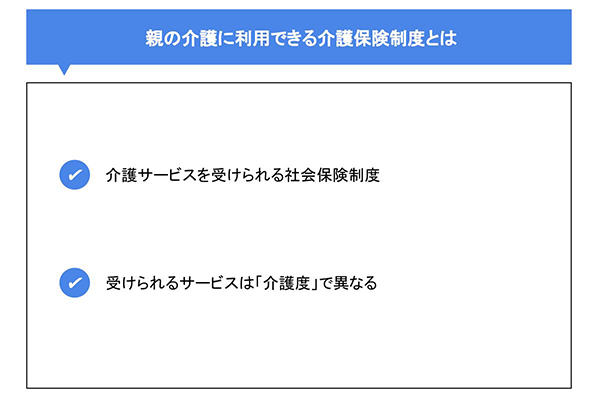
介護保険は、介護にかかる費用の一部を給付する制度です。この制度を利用すると施設入居やリハビリテーション、日常生活の支援など、介護サービスでかかった費用の自己負担額が10〜30%になります。
介護サービスを受けられる社会保険制度
介護保険制度は、40歳以上のすべての人に加入義務があります。65歳以上の方は「第1号被保険者」、40〜65歳の方は「第2号被保険者」と区分されています。「第1号被保険者」の場合は、年金から天引きされる形で、「第2号被保険者」は、健康保険と合わせて徴収されます。なお、介護保険料は会社が所属する保険組合と市区町村によっても異なります。
介護保険制度のサービスを受けられるのは、原則65歳以上の「第1号被保険者」です。ただし、「第2号被保険者」でも下記の特定疾病に該当する場合、介護保険制度の利用対象に含まれます。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
受けられるサービスは「介護度」で異なる
「介護度」とは介護の必要性を表した指標のことを言います。介護度は「要介護」「要支援」「非該当」の3つに分けられます。
要介護
「要介護」状態は、身体または精神における障害によって、6カ月以上にわたって誰かの介護なしには入浴や食事、排泄など、基本的な日常動作ができない状態を指します。要介護には1~5の5段階あり、数字が大きくなるほど介護の必要性が高いと判断されるため、受けられるサービスが増えて、支給限度額も高くなります。
要支援
「要支援」状態は、身体または精神における障害によって、6カ月以上にわたって入浴や食事、排泄など基本的な日常動作の一部に介護や支援が必要な状態を指します。要支援1、要支援2の2段階あります。こちらも要介護の指標と同様に、数字が大きくなるほど受けられるサービスが増えて、支給限度額も多くなります。
非該当
非該当とは、介護が必要な対象ではない、つまり自立して生活できる状態を指します。非該当と判定されると、介護保険のサービスを利用できない、または全額自己負担となります。
介護保険で受けられるサービス
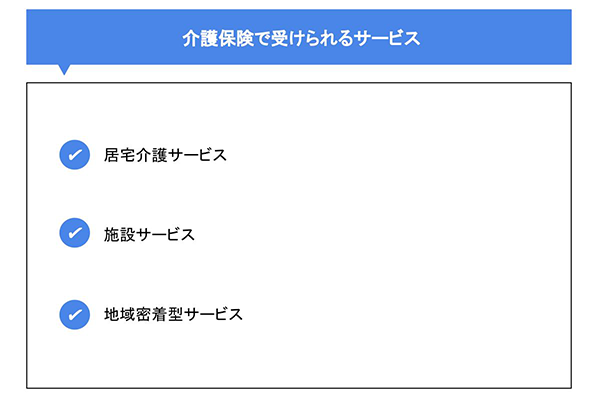
介護保険では、具体的にどのようなサービスが受けられるのでしょうか。サービスとしては、大きく以下の3つに分けられます。
居宅介護サービス
要介護・要支援認定の方が、自宅に住みながら利用できる介護サービスのことを言います。居宅介護サービスの中にも、ホームヘルパーさんが利用者の自宅を訪問してリハビリテーションや入浴介護を実施する「訪問型」、利用者が介護施設に日中通う「通所型」、1カ月など短期で入所する「短期入所型」があります。
施設サービス
施設に入居して介護を受けられるサービスのことを言います。施設サービスは大きく公的施設と民間施設に分かれ、さらにそのなかでもいくつか種類があります。
| 施設名 | 利用要件 | 特長 | |
|---|---|---|---|
| 公的施設 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 原則65歳以上で要介護3以上 | 入浴や食事、排泄などの日常生活に伴う介助サービスを提供 |
| 介護老人保健施設 | 原則65歳以上で要介護1以上 |
|
|
| 介護療養型医療施設 | 原則65歳以上で要介護1以上 |
|
|
| 介護医療院 | 原則65歳以上で要介護1以上 |
|
|
| 軽費老人ホーム | 家族の支援がない、身寄りがない60歳以上の方 |
|
|
| 民間施設 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 「一般型」は自立して生活できる非該当の高齢者、「介護型」は要介護1以上 |
|
| 有料老人ホーム(介護付・住宅型・健康型) | 「介護付」は要介護1以上、「住宅型」、「健康型」は自立可能な65歳以上 |
|
地域密着型サービス
2006年4月の介護保険制度改正に伴って設置された介護施設です。住み慣れた地域で継続して生活できるようにすることを目的としており、「夜間対応型訪問介護」「認知症対応型通所介護」「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」など、さまざまなタイプの施設があります。原則として、居住地以外の市区町村での利用はできません。
介護保険では提供されないサービス

介護保険が適用されるのは、生活支援や身体介護、リハビリテーションなどであり、日常生活に必要ではないと判断される行為については、介護保険の適用外となります。次のようなサービスは介護保険では提供されません。
- 送迎・移送
- 家事代行
- ペットの世話
- 訪問理容師
- 宅食 など
親の介護にはどのくらいのお金がかかる?

ここまで、介護保険制度と介護保険が適用されるサービスについて解説しました。では、具体的に、親の介護にはどのくらいのお金がかかるのでしょうか。生命保険文化センターの調査によると、住宅改造や介護用ベッドの購入費など介護に要した一時的な費用は平均74万円、管理費(水道光熱費)、居住費、食費など月々でかかった費用は平均83,000円となりました。
介護期間は平均61.1カ月とあることから、月々の費用合計だけでも500万円、一時費用を合わせると600万円弱かかる計算になります。
老後資金が足りないときは民間介護保険も検討
親の老後資金が足りない場合は、民間介護保険も視野に入れましょう。民間介護保険とは、生命保険会社が提供している介護保険で、公的な介護保険の不足分を補完する役割を担います。加入は任意で、給付金額も自ら設定することができます。また、40歳以下でも加入できて、早くから備えることができます。
まとめ

保険適用対象である介護施設の種類は多岐にわたり、介護保険の適用条件や仕組みを一度で理解しにくいですが、老後の支えとなる制度です。
常陽銀行では、WEB来店予約サービスを行っております。事前にご予約いただくことで、窓口に並ぶことなく、ご案内が可能です。
WEB来店予約サービスでは、
- 銀行手続きをほかの人に頼みたい
- 財産管理を家族・専門家に任せたい
- 事前に財産分与を決めておきたい
- 相続に備えた専門的なアドバイスがほしい
- 相続時、家族が引き出せるお金を準備しておきたい
などのお困り事などに対応しています。詳しくは下記よりご確認ください。
(2022年5月10日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以 上