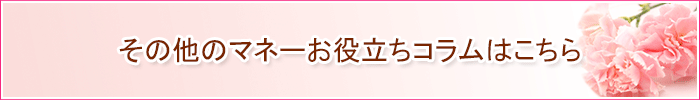高額介護合算療養費制度を分かりやすく解説!医療費や介護費を軽減しよう
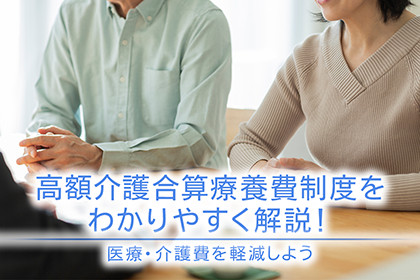
高額介護合算療養費制度は、医療・介護費用の負担に悩んでいる人にとって、とても重要かつ便利な制度です。この制度を利用すれば、医療費、介護費の自己負担額を軽減できます。受給資格や手続きの方法、実際に支給される額などを分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
高額介護合算療養費制度とはどういう制度?
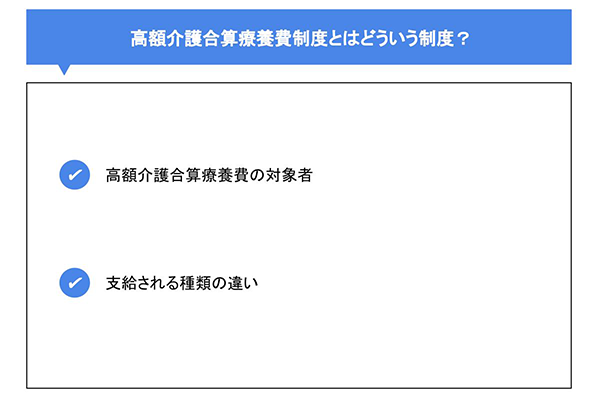
毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間の介護保険、医療保険の自己負担額が一定額以上の高額になった場合、自己負担分の費用を軽減できる制度が高額介護合算療養費制度です。この制度を活用すれば、生活費のうちに占める医療費、介護費用が膨らみすぎてしまう事態を防げます。医療費・介護費の捻出のために困窮状態に陥らないためにも、制度の詳細をしっかりと把握しておきましょう。高額介護合算療養費の対象者やその種類、申請方法について細かく説明します。
高額介護合算療養費の対象者
高額介護合算療養費の対象となる条件は次の通りです。
- 国民保険、被用者保険、後期高齢者医療保険を利用している人が同じ世帯内にいること。
- 1年間の医療保険と介護保険の合算額が、所得に応じた限度額を超えていること。
同一世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用していて、自己負担額が限度額を超えている場合、限度額を超えた分が返還されます。限度額は対象者の所得によって段階的に変わっていきます。
対象者の区分と負担上限額の内訳は次の通りです。
| 区分 | 負担の上限額 |
|---|---|
| 年収1,160万円以上 | 212万円 |
| 年収770万円以上1,160万円未満 | 141万円 |
| 年収370万円以上770万円未満 | 67万円 |
| 年収165万円以上370万円未満 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 区分 | 負担の上限額 |
|---|---|
| 年収1,160万円以上 | 212万円 |
| 年収770万円以上1,160万円未満 | 141万円 |
| 年収370万円以上770万円未満 | 67万円 |
| 年収165万円以上370万円未満 | 56万円 |
| 住民税非課税世帯 | 31万円 |
| 住民税非課税世帯(一定額以下) | 19万円 |
所得額によって負担の上限額が異なります。
支給される種類の違い
介護保険に関して支払った場合は「高額医療合算介護サービス費」、医療保険に関連する費用を支払った場合は「高額合算療養費」として支給されます。例えば入院した費用と介護の費用は合算して支給されますが、その両方の窓口の手続きが完了してからの支給になります。手続きが完了した後に、年齢や収入で支給額が決定し、合算した額が振り込まれます。
例)
- 要介護認定済の70歳の親が、介護保険を使用して介護施設に入所し、毎月10万円の自己負担が発生し、年間120万円が自己負担となった。
- 同居家族が入院し、医療保険を使用して入院した。その後の通院などで自己負担の年額が40万円となった。
上記のケースでは、医療サービスは医療保険者へ、介護サービスは介護保険者へ申請して、世帯の年間限度額を超えた額は高額介護合算療養費として支給されます。支払い窓口が違うため、両方の窓口の手続きが完了しないと支給されません。
高額介護合算療養費の限度額

高額介護合算療養費の世帯ごとの限度額は次の通りです。
| 後期高齢者医療制度+介護保険 | 被用者保険又は国保+介護保険(70歳~74歳がいる世帯) | 被用者保険又は国保+介護保険(70歳未満がいる世帯) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (上位所得者) |
67万円 | 67万円 | 126万円 |
| 一般 | 56万円 | 62万円 | 67万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 | 19万円 | 34万円 |
70歳未満の方と70歳~74歳の方が同じ世帯に同居していた場合は、まずは70歳~74歳の方の限度額を適用して支給されます。そしてなお残った負担額があった場合、70歳未満の方がいる世帯の限度額を適用して再度支給されます。その際の支給額については細かく設定されており、介護保険料や医療保険の利用状況や世帯の収入によっても変わってきます。同一世帯者の年齢と世帯の所得を照らし合わせて、正しい額を把握しておきましょう。
高額介護合算療養費の申請をするための手続き

次に、高額介護合算療養費の具体的な手続きになります。必要な書類が揃わないと申請が完了しないため、細かい流れをきっちりと知っておきましょう。
支給されるまでの流れ
まず、自分が高額介護合算療養費の対象者であるかを確認します。対象であれば必要書類を用意して提出します。支給されるまでの流れは次の通りです。
- 介護保険の被保険者は介護保険者(市町村)に「高額介護合算療養費支給申請遺書兼自己負担証明書」を提出する。
- 市町村から「自己負担額証明書」が交付される。
- 医療保険者(健康保険組合など)に「自己負担額証明書」を添付して支給申請を行う。
- 医療保険者が介護保険者に計算結果を連絡し、支給額が決定する。
- 支給額決定の通知が利用者に連絡され、支給される。
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担証明書は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
高額介護合算療養費の対象とならないもの

高額介護合算療養費の対象にならないものは次の通りです。
- 特定福祉用具
- 住宅改修
- 施設の居住費(短期滞在費)および食費
- 理美容などの日常生活にかかった費用
- 生活援助サービスの食費 など
もとより介護保険のサービス対象外の食費などに加えて、上記の項目は減額の対象にはなりません。
高額介護合算療養費が支給されるまでの期間

書類を提出してから証明書の発行、送付までの期間は自治体によってまちまちです。また、介護保険と医療保険は担当窓口が異なるため、交付までの時期にズレが発生します。市町村から介護負担証明書が発行されて自宅に届くまでの間もありますし、その後に届いた書類を添付して医療保険者に提出し、支給額算定を待つ必要があります。詳しく期間を知りたいという方は、保険者に確認してみましょう。
まとめ

高額介護合算療養費は保険利用者と自分の生活を守るための便利な制度です。年齢を重ねるごとに、入院のリスクや介護の必要性はだんだんと高まっていきます。医療費や介護費の自己負担を少しでも和らげるために、しっかりと活用して日々の生活を少しでも豊かに過ごしたいものです。調べる手間、交付までの期間の長さなどハードルは高いのですが、1つ1つ確実に処理を行い、きっちりと制度を活用していきましょう。医療保険や介護保険の負担額がいつ生活を圧迫するかは分かりません。そのためにも、十分な貯蓄は用意しておいたほうが良いでしょう。財産管理に関するお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
(2022年5月10日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以 上