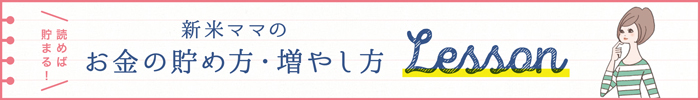子育てに必要な教育費はいくら?大学までの平均費用や貯め方を解説
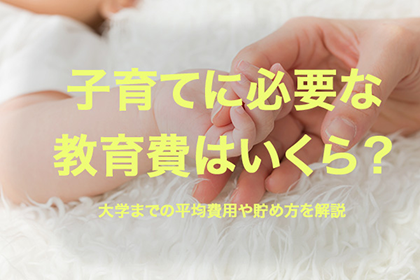
幼稚園から大学まですべて国公立に入学し、かつ実家から大学に通ったとしても、幼稚園から大学までで1,000万円以上の資金が必要です。私立に通わせる場合はそこから約2~3倍の費用がかかります。
教育費は、学校でかかるお金だけでなく、学習塾やスポーツの習い事など学校以外の活動費もすべて含めた費用です。
本記事では、これらの教育費の詳細と、確実に貯める方法について詳しく解説していきます。
幼稚園から大学卒業までにかかる費用

ではさっそく、実際に教育費がいくらかかるのか、幼稚園から大学まで個別にみていきましょう。まずは幼稚園の1年間の教育費から解説します。
幼稚園に通っている子どもにかかる1年間の教育費
「令和3年度子供の学習費調査」によれば、幼稚園に通っている子どもにかかる1年間の教育費は、以下のとおりです。
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 学習費総額 | 165,126円 | 308,909円 |
| ・うち学校教育費 | 61,156円 | 134,835円 |
| ・うち学校給食費 | 13,415円 | 29,917円 |
| ・うち学校外活動費 | 90,555円 | 144,157円 |
調査の結果では、幼稚園の教育費は公立が1年間で165,126円、私立が1年間で308,909円となりました。公立と私立では、約2倍の差があることが分かります。
小学校に通っている子どもにかかる1年間の教育費
続いて、小学校に通っている子どもにかかる1年間の教育費は、以下のとおりです。
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 学習費総額 | 352,566円 | 1,666,949円 |
| ・うち学校教育費 | 65,974円 | 961,013円 |
| ・うち学校給食費 | 39,010円 | 45,139円 |
| ・うち学校外活動費 | 247,582円 | 660,797円 |
公立の小学校の場合の教育費の平均は1年間で352,566円、私立が1年間で1,666,949円となりました。
公立と私立とでは、教育費は約5倍と大幅に変わることが分かります。とくに、学校教育費と学校外活動費に大きな差が出ています。上記をふまえて、子どもを私立の小学校に通わせる場合は、十分に資金を準備しておく必要があるでしょう。
中学校に通っている子どもにかかる1年間の教育費
続いて、中学校の場合の1年間の教育費について紹介します。
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 学習費総額 | 538,799円 | 1,436,353円 |
| ・うち学校教育費 | 132,349円 | 1,061,350円 |
| ・うち学校給食費 | 37,670円 | 7,227円 |
| ・うち学校外活動費 | 368,780円 | 367,776円 |
中学校の教育費の平均額は公立が1年間で538,799円、私立が1年間で1,436,353円となりました。
公立と私立では、約2.5倍ほどの違いがあることが分かります。一般的に、私立中学校ではお弁当のため、学校給食費が公立に比べ安くなっていますが、学校教育費に関しては約8倍と大きな差が出ています。
高等学校に通っている子どもにかかる1年間の教育費
高等学校に通っている子どもにかかる1年間の教育費は、以下のとおりです。
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 学習費総額 | 512,971円 | 1,054,444円 |
| ・うち学校教育費 | 309,261円 | 750,362円 |
| ・うち学校外活動費 | 203,710円 | 304,082円 |
高校生の1年間の教育費は公立で512,971円、私立で1,054,444円となりました。公立と私立では、約2倍の差があるということが分かります。
学校外活動費は約1.5倍、学校教育費で約2.5倍と私立の方が高い結果となっています。ただし私立の高等学校の教育費は、小学校や中学校と比べて、公立との差が小さいことが分かります。
大学生にかかる教育費の総額
大学生にかかる教育費の総額は、以下のとおりです。
| 国公立大学 | 私立大学文系 | 私立大学理系 | |
|---|---|---|---|
| 卒業までに必要な 入在学費用 |
4,812,000円 | 6,898,000円 | 8,216,000円 |
| ・入学費用 | 672,000円 | 818,000円 | 888,000円 |
| ・在学費用 | 4,140,000円 | 6,080,000円 | 7,328,000円 |
日本政策金融公庫の2021年度「教育費負担の実態調査結果」によると、大学卒業までの教育費用は国公立で平均4,812,000円、私立大学文系で平均6,898,000円、私立大学理系で平均8,216,000円となっています。
ここでも、国公立と私立の間では少なくとも200万円以上と大きな教育費の差が生じています。とくに私立大学の場合は、子どもが文系か理系どちらを選ぶのかによっても大幅に費用が異なります。
また、大学進学と同時に一人暮らしをする場合は、さらに引越し資金(約39万円)や仕送り(年間約96万)が必要になるので、4年制の大学なら39万円+96万円×4年=約423万円が別途必要になりますので注意が必要です。
子どもを大学まで通わせると、低めに見積もっても500万円は必要になると想定しておきましょう。
トータルでかかる教育費
それでは、幼稚園から大学卒業までにかかる教育費は合計でいくらになるのでしょうか。下表に「公立か、私立か」と「大学は実家から通学か、一人暮らしか」の4種類のパターンで費用を集計しました。
| 国公立(大学は実家から通学) | 国公立(大学は一人暮らし) | 私立文系(大学は実家から通学) | 私立文系(大学は一人暮らし) | |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 472,746円 | 924,636円 | ||
| 小学校 | 2,112,022円 | 9,999,660円 | ||
| 中学校 | 1,616,317円 | 4,303,805円 | ||
| 高等学校 | 1,543,116円 | 3,156,401円 | ||
| 大学 | 4,812,000円 | 9,031,000円 | 6,898,000円 | 11,117,000円 |
| 教育費総額 | 10,556,201円 | 14,775,201円 | 25,282,502円 | 29,501,502円 |
幼稚園から大学まですべて国公立に入学し、かつ実家から大学に通ったとしても、幼稚園から大学までで1,000万円以上の資金が必要になります。私立に通わせる場合はそこから約2~3倍の費用がかかることを覚えておきましょう。
教育費として必要な貯金額

高校卒業までの教育費は、可能であれば月々の給料やボーナスの中で支払っていくと良いでしょう。
しかし大学や専門学校の入学時には授業料も前期、後期などまとめて支払う必要が出てきます。また一人暮らしをする場合は、引越し代や敷金・礼金、食費、光熱費も必要になります。そうなると一度に大きな額の出費が発生することになるので、あらかじめ貯蓄で備えておく必要があるでしょう。
日本政策金融公庫の調査によれば、大学入学の1年目にかかる教育費の平均額は231万円という結果が出ています。そのため、大学入学までに可能であれば250万円程度は貯蓄しておくと良いでしょう。また、前述のとおり、大学の卒業までにかかる学費は、国公立でも4年間で500万円程度、私立大学文系では700万円程度、理系は820万円程度となっています。入学後の学費の支払いをまかなえるか、シミュレーションしておくようにしましょう。
教育費を貯めるには?
ここまで、大学卒業までに教育費がいくらかかるのかの相場を説明してきましたが、実際にどのように資金を調達すれば良いのでしょうか。ここでは、教育費を貯める方法について解説していきます。
定期預金や積立定期預金をする
教育費を貯める方法として、定期預金や積立定期預金を行う方法があります。
- 定期預金:期間を定めて行う預金サービス
- 積立定期預金:毎月決まった日にお金を預ける預金サービス
定期預金や積立定期預金は、解約しない限り簡単には引き出せないので、貯金が苦手な方でもお金を貯めやすいという特徴があります。ただし、最近では低金利が続いているため、ほとんど金利は付きません。そのため、積み立てた分は確実に貯蓄できますが、積み立て分以上はほとんど増えないと思っておいた方が良いでしょう。
金利は付かないが、確実にお金を貯めたいのであれば、定期預金や積立定期預金は有効な方法です。
学資保険に加入する
教育費を貯める方法として、学資保険に加入する方法もあります。
学資保険とは、子どもの教育費を準備するための貯蓄型の保険のことです。保険料を支払い続けることで子どもの学費を準備することができ、手元にお金があると使ってしまうような方に向いています。一方で、払い込んだ総保険料よりも満期金が低い保険商品もあるので、加入時にはよく注意しましょう。
また、学資保険は両親が死亡した際のリスクに備えることができるのも利点です。
万が一、両親が死亡してしまった場合、何も対策をしていなければその後の教育費の支払いが難しくなるでしょう。貯蓄をしていたとしても、死亡した時までの貯蓄額では、本来準備したかった教育費を用意できないことも考えられます。
しかし、学資保険で「保険料払込免除」の契約を結んでいれば、契約者が死亡してしまった場合、それ以降の保険料の支払いが免除となります。かつ、満期時には契約時に決めていたとおりの保険金を受け取ることができるのです。
ただし学資保険は、途中解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)が、支払った保険料の総額よりも少なくなるのが一般的です。保険料の支払いについては無理のない設定が必要です。
NISAで投資する
教育費を貯める方法として、NISAで投資を行うのも一つの方法です。
NISAとは、投資によって得られた利益が非課税になる制度です。2024年から新しいNISA制度が始まり、年間の投資上限金額が360万円になったり、非課税保有期間が無期限になるなどより長期的な資産形成がしやすい制度になりました。
NISAでは毎月一定額を積み立てていく「積立投資」と好きなタイミングで投資する「一括投資」という方法があります。
子どもの成長に合わせて毎月コツコツ積み立てをしながら、ボーナスなどまとまったお金が入った時は一括で投資するなど、柔軟に資産形成を行うことができます。また、いつでもお金を引き出すことができるので、急にお金が必要になった時でも心配いりません。
NISAの非課税メリットを活用しながら効率よく資産形成してみませんか?
NISAについてはこちら教育費が足りないときは?
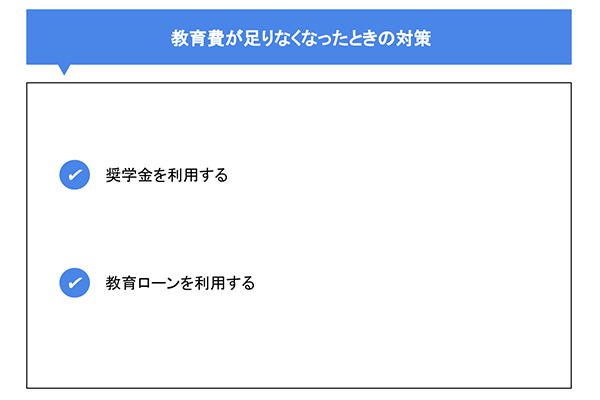
ここまで説明した方法で教育費を貯めていても、急な出費が発生し教育費が足りなくなるということも、人生においては十分にあり得ます。ここでは、万が一教育費が足りないときにどうすれば良いのかを解説します。
奨学金を利用する
教育費が十分に貯められていない場合は、奨学金の活用を検討しましょう。奨学金には2種類あり、返済が不要な「給付型」と返済が必要な「貸与型」があります。
給付型は返済が必要ないというメリットがある分人気が高く、一定の成績水準を満たしていなければ応募ができないなど、受給者は限られるのが一般的です。ただし、高校や大学独自に給付型の奨学金を準備している場合があるので、最初からあきらめずに、問い合わせてみると良いでしょう。
貸与型には利子が発生するものと無利子のものとがあり、それぞれ応募条件が異なるので注意しましょう。大抵の場合は、貸与型の奨学金を検討する必要があるため、事前に子どもとよく話し合う必要があります。
教育ローンを利用する
奨学金以外では、教育ローンを活用するという選択肢もあります。用途は教育に関するものであれば幅広く認められており、入学金や授業料はもちろん、留学や一人暮らしのための費用にも使うことができます。
教育ローンを検討しているのであれば、常陽銀行が提供する教育ローンがおススメです。条件に合えば、茨城県外に住んでいる方でもお申し込みができることや、最大1,000万円までお申し込みをすることができます。興味のある方は、ぜひお気軽に窓口やお電話でご相談ください。
教育ローンについてはこちら大学まで進学する場合は早めの資金準備が必要
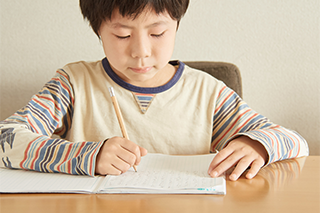
子どもの教育費は、大学まで進学する予定なのであれば、国公立に進学したとしても1,000万円は準備しておく必要があります。また、文系・理系どちらを選ぶのかによっても大きく左右されるので、子どもの進路についてもよく話し合う必要があるでしょう。
貯蓄だけで資金の準備ができるか不安な方は、奨学金の活用ができないかを確認しつつ、定期預金や学資保険、NISAなどの利用も検討しましょう。
(2025年8月8日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以 上