新NISAの成長投資枠とは何?概要や活用法、つみたて投資枠との違いを解説

資産形成の一環として、新NISAを活用している・活用を検討している人は多いでしょう。新NISAでの資産運用をより充実させるには「成長投資枠」の活用も1つの方法です。
成長投資枠とは2024年に開始した新NISAにおける投資枠の1つです。投資信託のほか、株式やETF(上場投資信託)に投資でき、年間投資枠は240万円までとなっています。
この記事では、新NISAの成長投資枠の概要やつみたて投資枠との違い、成長投資枠の活用方法について解説します。
新NISAの成長投資枠とは

新NISAの成長投資枠は、旧NISA制度の一般NISAの後継とも言える枠です。NISAのもう1つの枠である「つみたて投資枠」との併用も可能です。
成長投資枠の年間投資枠は240万円、生涯にわたる非課税保有限度額は1,200万円までとなっています。投資額が限度額を超過した場合は、課税口座(特定口座や一般口座)での買付となります。
成長投資枠で投資できる商品は、投資信託のほか、株式やETFなどです。つみたて投資枠は国が定めた基準を満たす投資信託や一部のETFしか購入できないため、成長投資枠はより自由度の高い投資ができるのが特徴です。
ただし、債券や毎月分配金が支払われるタイプの投資信託は、成長投資枠であっても購入できません。
新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠を比較
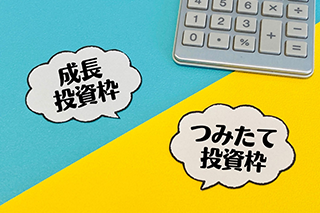
新NISAは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つの枠が設けられています。それぞれの違いを見ていきましょう。
| 項目 | 成長投資枠 | つみたて投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税保有限度額 | 1,200万円 (総枠1,800万円のうち) |
生涯で1,800万円(総枠) |
| 投資対象商品 | 投資信託、上場株式、ETFなど (一部除外あり) | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定) |
成長投資枠は年間投資枠が大きく投資対象商品も幅広いです。成長投資枠を使えば、積立投資のほか、個別株式の売買や高配当株式・高配当ETFによる配当金の受け取りなど、多様な投資スタイルに挑戦できます。ただし、生涯にわたる非課税保有限度額は1,200万円までと決められています。
一方、つみたて投資枠は、投資できる商品が長期の積立・分散投資に適したものに限定されており、個別株などへの投資はできません。
新NISAの成長投資枠を使うメリット

新NISAの成長投資枠を使うメリットは以下のとおりです。
- 購入できる商品が増えて投資の選択肢が広がる
- 積立購入と一括購入を自由に選べる
- つみたて投資枠との併用で年間投資可能額が増える
メリットをそれぞれ解説します。
購入できる商品が増えて投資の選択肢が広がる
成長投資枠では、投資信託・株式・ETFなど、つみたて投資枠よりも購入できる商品が増えるため、投資の選択肢が広がります。
株式では国内株式や外国株式が購入できるため、大手企業の株式を保有したり、配当利回りの高い株式を購入してまとまった配当金を得たりする投資が可能です。ETFも国内外のものが購入できるため、積み立てや配当狙いなど、自分の目的に合わせた投資ができます。
積立購入と一括購入を自由に選べる
成長投資枠では、投資方法を「積立」か「一括(スポット購入)」か自由に選択できます。つみたて投資枠では積立投資のみ可能ですが、成長投資枠なら投資信託や株式を一括で購入できるため、投資の選択肢がさらに広がります。
まとまった資金で一括で購入すれば、相場が上昇したときに大きな利益が出やすくなります。一方、下落時の損失額も大きくなるため、購入のタイミングや購入銘柄の見極めも重要です。
つみたて投資枠との併用で年間投資可能額が増える
成長投資枠は年間240万円まで投資ができます。
年間120万円まで投資できるつみたて投資枠と合わせれば、年間で最大360万円まで投資ができます。つみたて投資枠と成長投資枠を併用すれば、毎月の積立額をさらに増やすことも可能です。
新NISAの成長投資枠を使うデメリット

新NISAの成長投資枠を利用するデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 非課税保有限度額をすべて使い切ることはできない
- リスクの高い銘柄に注意しなければならない
成長投資枠を活用する際は、リスクや上限額に注意が必要です。デメリットをおさえて、賢く活用しましょう。
非課税保有限度額をすべて使い切ることはできない
新NISAの生涯非課税保有限度額は1,800万円ですが、成長投資枠だけで利用できる上限額は1,200万円です。そのため、成長投資枠の利用だけでは、非課税保有限度額の上限すべてを活用することはできません。限度額をすべて活用するには、つみたて投資枠との併用が必須です。
リスクの高い銘柄に注意しなければならない
成長投資枠は購入できる商品が増える分、値動きが大きい銘柄が含まれている可能性があります。
つみたて投資枠の対象商品は、「長期・積立・分散投資」に適しているといった金融庁が定めた基準を満たした投資信託です。信託契約期間が長く、手数料が低いなどの条件をクリアした銘柄がラインナップされています。
しかし、成長投資枠の対象銘柄には上場株式や、指数を上回る収益を目指すアクティブファンドなども含まれます。銘柄によっては、手数料が高かったり、値動きが激しかったりする場合があるため、購入前によく確認すると良いでしょう。
新NISAの成長投資枠の上手な活用方法
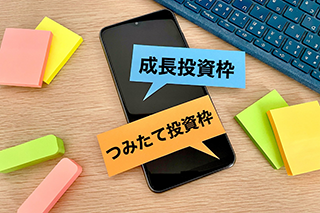
新NISAの成長投資枠を上手に活用するには、つみたて投資枠との併用や、つみたて投資枠とは異なる投資方法を取るのが良いでしょう。上手な活用方法を解説します。
つみたて投資枠と違う銘柄を積み立ててリスクを減らす
つみたて投資枠とは違う銘柄を積み立てれば、さまざまな地域や資産に投資できるため、分散投資が実現でき、特定の資産が暴落した際の損失を抑える効果が期待できます。
例えば、つみたて投資枠で米国の株価指数に連動するファンドを積み立てている場合、成長投資枠で日本の株価指数や新興国の株価指数に連動するファンドを積み立てると地域が分散されます。これにより、どちらかの地域の株価が下落したときも、もう一方でカバーでき、損失を小さく抑える可能性があるのです。
リスクを減らしながらコツコツと資産を増やしていきたい人に、適した手法といえます。常陽銀行を例にすると、バランス型の投資信託や、金価格に連動した値動きをする投資信託は下記のような銘柄があります。
- のむラップ・ファンド(普通型)
- 日経225ノーロードオープン(※ネット専用)
- ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
つみたて投資枠と同じ銘柄の積立額を増やす
つみたて投資枠と同じ銘柄の積み立てを成長投資枠でも行えば、より効率良く資産運用ができます。
成長投資枠は年間240万円、毎月20万円まで積立投資が可能です。つみたて投資枠の毎月10万円と合わせると、合計で毎月最大30万円まで積立投資ができます。まとまった資金を用意できるのであれば、より効率の良い資産形成が可能になるでしょう。
この方法で運用する場合は、成長投資枠・つみたて投資枠どちらの買付にも対応しているものを選ぶのがおススメです。例えば、常陽銀行では以下のような銘柄が対象です。
- のむラップ・ファンド(積極型)
- 日経平均高配当利回り株ファンド
- ひふみプラス
配当金・分配金を受け取る
積立投資だけでなく、配当金や分配金を受け取ることができる点も、成長投資枠の魅力の1つです。配当利回りの高い株式や、高利回りの投資信託にまとまった資金を投資することで、株主や投資信託の保有者として「配当金」や「分配金」を受け取ることが可能です。
ただし、配当金や分配金は投資金額に比例して受け取れるため、多く受取りたい場合は、まとまった資金が必要になります。また、投資対象の運用成績によって配当や分配金が必ず受け取れる保証はない点には注意しましょう。
長期保有に適した銘柄を選んでじっくり資産をつくる
長期保有に適した銘柄を成長投資枠でも選び、長い目で投資するのも方法の1つです。NISA口座は売却するとその分の非課税枠が翌年以降に復活しますが、頻繁な短期売買を想定して設計されている制度ではありません。
中長期的な保有を前提として、株式と債券など異なる資産クラスに分散投資するバランスファンドや特定の指数に連動するインデックスファンドなどに積み立てで投資すれば、より安定したリターンを実現できる可能性があるでしょう。
成長投資枠とつみたて投資枠を使い分けて資産運用する
成長投資枠とつみたて投資枠の併用の仕方はさまざまです。上記で説明した活用方法をもとに併用の仕方をまとめると、以下の通りとなります。
| 併用の仕方 | 適している人 |
|---|---|
| 両方の枠で異なる銘柄を積立投資する | 銘柄を分けることで、さまざまな資産や地域に分散投資できます。リスクを抑えながら長期的に利益を狙いたい人、セカンドライフなどまだ遠い将来の資産をつくりたい人に適しているでしょう。 |
| 両方の枠で同じ銘柄を積立投資する | 同じ銘柄で運用して利益が出た場合、運用する元本が多いほど、運用利益も大きくなります。より多くの金額を積み立てしたい人に適しているでしょう。 |
| 積立投資と配当投資を組み合わせる | 将来の資産をつくりながら、現在の生活で使えるお金を増やしたい人に適しているでしょう。 |
自分に合った方法で、資産形成を進めていきましょう。
新NISAの成長投資枠を利用する際の注意点

新NISAの成長投資枠を活用する際は、以下の2つに注意したいところです。
- 銀行では株式の購入ができない
- 購入する銘柄の特徴をよく把握する
銀行では株式の購入ができない
銀行では法律により株式の直接的な取り扱いが認められていません。そのため、銀行のNISA口座の成長投資枠で購入できるのは、投資信託のみとなります。株式を積み立てたい人や高配当株に投資したいと考えている人にとっては、銀行でのNISA利用は不向きかもしれません。
ただし、銀行の投資信託のラインナップによっては、実質的に配当が受け取れるような投資信託を提供している場合があります。また、つみたて投資枠で買付できる優良な銘柄を、成長投資枠で追加購入することも可能です。
加えて、目当ての株式が含まれる日経平均株価やS&P500といった指数への投資は、投資信託を通じて実現できます。そのため、積立投資を中心に考えている人にとっては、大きなデメリットにはならないでしょう。
購入する銘柄の特徴をよく把握する
成長投資枠ではさまざまな銘柄を購入できるため、それぞれの特徴をよく把握しておく必要があります。例えば、株式なら業種やこれまでの業績、今後の事業見通しなどを理解しておくことが大切です。投資信託なら、連動する指数や購入手数料、分配金の有無などを確認しましょう。
過去の値動きなどから、変動が激しいものはリスクが高い場合があります。投資する際は、株価下落時の対策や、現在のポートフォリオで他銘柄への分散ができているかなどをよく確かめたうえで判断をすると良いでしょう。
新NISAは銀行とネット証券どちらで利用するのが良い?

新NISAの成長投資枠活用にあたって、金融機関選びも大切になってきます。NISA口座はネット証券や銀行で開設できます。それぞれの特徴を見てみましょう。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| ネット証券 |
|
|
| 銀行 |
|
|
銀行はネット証券に比べて、口座開設後のサービスの充実度や、対面で相談できる安心感などがあります。成長投資枠はつみたて投資枠より自由度が高い分、リスクもつきまとうものです。少しでも不安を解消したい人は、銀行員のアドバイスを受けながら投資ができる銀行でのNISA利用が適しているでしょう。
新NISAの成長投資枠に関するよくある質問

新NISAの成長投資枠に関する質問・疑問をまとめました。
新NISAの成長投資枠で購入したいおススメ銘柄はありますか?
成長投資枠で購入したいおススメの銘柄は、個人の投資計画や目的によって異なります。成長投資枠は、積立投資に適した銘柄に加え、配当金の受け取りが期待できる銘柄も存在します。
自分が長期的に資産をつくりたいのか、配当で現在の生活を潤したいのか、どの地域や指数に投資したいのかなどを軸に購入銘柄を選べば、思い描いていた投資計画や目的を実現できるでしょう。
もし銘柄選びに困った場合は、銀行などの金融機関に相談すると良いでしょう。
\平日20時まで、土曜日も可能/
資産の売却後に新NISAの成長投資枠が復活するのはいつですか?
新NISAでは、資産を売却するとその分の非課税枠が復活します。枠が復活するのは、売却した年の翌年です。売却した年はその分だけ非課税枠が減ったままになるため、同一年内に再購入や積立を行う際には注意しましょう。
新NISAの成長投資枠での積み立て設定はどのようにしますか?
成長投資枠の積み立て設定は、NISA口座を開設した金融機関のアプリやインターネットバンキング、店舗などで手続きできます。
新NISAの成長投資枠を活用して自分に合った資産形成を

新NISAの成長投資枠は、上手に活用すればより多くの資産を用意できる便利な制度です。つみたて投資枠と併用も選択肢に入れながら、ライフステージに合った資産形成プランを立てていきましょう。
常陽銀行では、口座開設手続きだけでなく、ライフステージに合わせた資産形成プランの相談が可能です。成長投資枠の活用方法に悩んだ時には、相談してみると良いでしょう。
\平日20時まで、土曜日も可能/
(2025年11月18日)
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
以上