-
天引きだから手間いらず
財形預金【ざいけいよきん】
「財形預金」とは、「勤労者財産形成預金」の略称。民間企業に勤める会社員や公務員が対象となり、勤め先を通じて申込むことが可能です。給料や賞与から天引きされるため、無理なく、堅実に貯蓄することができるのが最大の特長。しかも、税金面での優遇や融資制度などメリットも多数あります。常陽銀行では、一部引き出しもできる「一般財形預金」、非課税で住宅資金を有利に貯められる「財形住宅預金」、個人年金として利用できる「財形年金預金」の3種類があります。家庭のライフプランに合わせて上手に利用しましょう。常陽銀行の財形預金はコチラ!
-
まとまったお金を効率よく運用
定期預金【ていきよきん】
定期預金とは、普通預金よりも金利が高く貯蓄に向いた預金です。普通預金と異なり、原則一定期間は引き出すことができませんが、その分確実に貯蓄ができます。追加の預け入れは可能なので、生活費用の口座と貯蓄用の口座を今後しっかり分けたい人や、ある程度まとまった金額を普通預金に入れっぱなしになっている人は、一考の価値ありです。預け入れ期間と金額によって利率が変わり、当行では貯蓄プランに合わせて1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、10年から預け入れ期間を選ぶことができます。自動継続を指定すれば満期日の手続きも不要で、わずらわしさもありません。
-
外貨の方が金利が高い!?
積立外貨預金【つみたてがいかよきん】
外貨預金とは、米ドルやユーロなど、外国の通貨での預金を指し、日本円よりも相対的に金利が高いため人気があります。預ける通貨は異なりますが、基本的な仕組みは円預金とあまり変わりません。ただし、為替手数料がかかるため、為替の変動がなかった場合でも元本割れとなる可能性があります。日本円から外国の通貨に変換するレート(為替レート)の上下動により、儲かったり損をしたりする仕組みです。為替は変動するため、元本割れリスクはあります。まずは、当サイトの「かんたん10秒体験」でシミュレーションをしてみましょう。
また、当行には、外貨の「自動つみたてプラン」がございます。ご指定の普通預金口座などから外貨貯蓄預金口座へ、毎月一定金額を自動的に振替ができるので着実に残高を増やせる上、入金する手間もかからない大変便利なサービスです。常陽銀行の外貨預金はコチラ!常陽銀行の外貨積立預金はコチラ! -
少ないお金でも投資はできる
積立投資信託【つみたてとうししんたく】
まとまった資金がなくても、月々1000円から始めることができる投資です(店頭では、最低5,000円からとなります)。自動引落で手間いらずなのも嬉しいところ。つい使ってしまう前に、お金を自動的に投資に回すことができます。また、購入のタイミングが分散されるのもメリットのひとつです。一括で投資した場合は、購入した基準価額以上にならないと利益が出ません。ですが、積立投信は毎月分割して購入するので、自動的に「安い時にも買っている」ことになり、購入価額を平準化できます。そういった点でも、毎月定額を自動的に購入する積立投資信託は初心者に始めやすい投資といえるでしょう。関連記事「積立投資でお金を貯める!初めての方の投資信託とは」関連記事「実は少額からできる投資信託」
-
妊婦健診14回分の費用が助成される
妊婦健診の助成制度【にんぷけんしんのじょせいせいど】
少子化対策の一環として、国から地方自治体におりるようになった予算のひとつが妊婦健診の助成制度です。妊婦健診は週数によって割合と回数がある程度決められています。費用は病院によりますが、通常の健診で5000〜8000円、採血や超音波など特殊な検査が必要な場合は2万円以上がかかることも。こうした経済的な負担が妊娠・出産を諦める要因にならないよう、2009年から妊婦健診14回分の費用が助成されることになりました。残念ながらまだ完全無料化には至っておらず、地方によって助成額も方法も違うのが現状です。
-
産休中の生活資金がもらえる
出産手当金【しゅっさんてあてきん】
会社員として仕事をしているママは、産休(産前に42日、産後に56日)を取ることができます。その間はお給料が出ない会社が多いため、生活を支える資金として健康保険から支給されるのが出産手当金です。出産後も仕事を続ける女性が対象となり、正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトでも健康保険に加入していれば受け取ることが可能。職場から申請用紙をもらい、産後、医師に必要事項を記入してもらって健康保険の加入先へ提出すれば、およそ1~2か月後に一括で振り込まれます。気になる手当額は、《標準報酬日額×2/3×休んだ日数分》となります。ただし、産休中にお給料が支払われる場合は、その分を差し引くので、標準報酬日額の2/3以上の給料をもらえる場合は出産手当金は受け取れません。関連記事「出産手当金はいくらもらえる?計算方法や手続きの流れを解説!」
-
1児出産につき42万円
出産育児一時金【しゅっさんいくじいちじきん】
健康保険の加入者で、出産した女性が1児につき42万円が支給される制度です。(産科医療補償制度に加入していない産院での出産の場合は39万円)専業主婦でも、夫の健康保険の扶養者であれば受け取ることができます。産院宛に直接振り込んでもらいたい場合は、出産予定日の前に産院と直接支払い制度に関する合意文書を取り交わす必要があります。受取代理制度の場合は、出産予定日前の2か月以内に受取代理申請書を、各健康保険組合、協会けんぽの都道府県支部、国保ならば市区町村役所へ提出します。出産前でなく産後に申請する場合は出産後すぐに手続きをしましょう。関連記事「出産育児一時金直接支払制度の概要と活用するメリットと注意点」
-
支給額は月給のおよそ半分!?
育児休業給付金【いくじきゅうぎょうきゅうふきん】
育児休業期間中に生活をサポートするため、月給の50%あるいは67%が支給される雇用保険の制度です。対象となるのは育児休暇を取るママとパパ。育児休業に入る前の2年間のうち、11日以上働いた月が11か月以上あり、雇用保険に加入して保険料を支払っている人です。育児休業を取らない人や育児休業終了後に会社をやめる場合は対象となりません。また、育児休業中に給料が8割以上もらえる場合ももらえません。育児休業給付金の支給額は、育児休業開始から180日までは月給の67%、181日目以降は50%というのが基本です。ママとパパの両方が育児休暇を取る場合は、180日以内の取得が有利ですので、お互いのタイミングを相談するのが得策です。関連記事「育児休業給付金とは?必要書類や申請方法を解説!」
-
もしものために備えよう
入院給付金
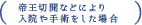 【にゅういんきゅうふきん】
【にゅういんきゅうふきん】医療保険に加入することで、入院した際に保険会社から給付される入院給付金、手術を受けた際の手術給付金は帝王切開の場合にも支払い対象となります。自然分娩の入院は給付対象外ですが、重度のつわりや切迫早産による入院でも給付金は支払われます。また、2回目以降の出産に備えて医療保険の加入を検討する場合、一度帝王切開をすると、基本的に2回目以降も帝王切開となるため、帝王切開後は一定期間契約不可となる保険会社も少なくありません。月々2000円以内の負担で入れる医療保険も多くあるので、結婚したタイミングや妊娠を希望したタイミングで加入しておくと安心です。医療保険・がん保険はコチラ!
-
中学生以下が対象です
児童手当【じどうてあて】
児童を養育する人に対して支給される手当で、日本では1972年から始まっています。2012年からは中学生(15歳に到達してから最初の年度末まで)以下を対象に、月額1万5000円あるいは1万円を受け取ることができますが、世帯所得や、子どもの人数などでも変わってきます。所得制限の対象となった場合は子どもひとりあたり月額5000円です。一般的には、父母のうちの所得が高いほうが手当の受給者となりますが、自治体によっては子どもの健康保険を負担している側となる場合もあります。出産後、住んでいる場所の自治体に申請すると、申請翌月からもらえるようになります。忘れてしまうと遡って受給することはできないので、早めの手続きを。
-
病院の領収書は捨てないで!
医療費控除
 【いりょうひこうじょ】
【いりょうひこうじょ】その年の1月1日から12月31日までに、一世帯で、年間10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額×5%の額)以上の医療費がかかった場合、超えた分の金額を所得から差し引き、税金から控除してもらうことができます。確定申告をする必要がありますが、還付金が受け取れることを考えるとやる価値は十分にあります。保険金や出産育児一時金などで補填された金額は差し引かれますが、妊娠中の定期健診や出産費用、助産師による分娩の介助料なども控除対象となるので、確定申告時に必要となる病院の領収書はしっかりと保管しておきましょう。
-
子どもにかかる費用
養育費・教育費【よういくひ/きょういくひ】
養育費とは、子どもを守り、育てるために必要な費用をいいます。一般的には、経済的・社会的に、子どもが成人して自立できるようになるまでにかかる費用のことで、衣食住、医療費、教育費などがこれに当たります。教育費は、学校にかかる費用に加え、教育全般にかかるお金を指します。文部科学省の定義では、①学校教育費(授業料、PTA費、修学旅行積立金、制服費、通学費など)、②学校給食費、③学校外活動費(学習塾、家庭教師費用、参考書購入費用、習い事の費用)のすべてを含めたものとなっています。教育ローンはコチラ!
-
収めている税額によって変わります
入園保護者補助金・就園奨励費(私立幼稚園入園費・保育料への補助)【にゅうえんほじょきん/しゅうえんしょうれいひ】
子どもにかかる学費は両親の大きな負担のひとつです。特に大学進学に際しては、相当な額を一度に用意することになります。なので、子どもにまだあまりお金がかからない小さいうちから積み立てておく貯蓄型の生命保険が学資保険(または子ども保険)です。期間途中で何か予想外のアクシデントがあっても当初の計画通り教育資金を確保できること、進学時期に合わせて支払期間を設定できることから、人気の理由となっています。将来、学費が理由でこどもの可能性を潰すようなことが無いよう、出産を控えているなら検討すべき保険のひとつといえるでしょう。
-
自治体が行っている助成制度
子ども医療費助成(乳幼児医療費助成・義務教育就学時医療費助成)【こどもいりょうひじょせい】
子ども医療費助成は、自治体が行っている助成です。自治体によりますが、たとえば茨城県の場合は、小学校3年生までの小児で、その父または母などの所得が一定金額以下であり、国民健康保険などの各医療保険に加入している場合、県内の病院や診療所などにかかるときに、保険証と一緒に医療福祉費受給者証を提出すれば、外来の場合は保険医療機関等ごとに1日につき600円(月2回を限度、3回目からは無料)、入院した場合は保険医療機関ごとに1日300円(月3,000円限度)の自己負担金を払うことで医療等を受けることができます。※この制度の適用を受けるには、住所のある市町村に小児の加入している保険証と印鑑を持参して、医療福祉費受給者証の交付を受けることが必要です。自治体によっては、入院時の食事標準負担額を助成してくれるところ、そうでないところなど差があるのが現状です。受給資格や申請方法、助成の開始日も自治体によって違うので、住んでいる自治体の制度がどうなっているか一度調べてみましょう。
-
1500万円までは非課税
教育資金の一括贈与【きょういくしきんのいっかつぞうよ】
平成25年4月1日から始まった教育資金の一括贈与は、子どもや孫へ教育資金を贈与する場合、1500万円までなら非課税となる制度です。上手に利用すると、相続税の節税対策に効果的なため、大きな反響がありました。子や孫に毎年コツコツ贈与する暦年贈与の場合、1500万円を贈与すると470万円の贈与税がかかりますが、教育資金の一括贈与制度ではこの税金が0円になります。ですが、贈与された人が30歳までに教育資金として使い切れない場合は通常の贈与税がかかるので要注意。ここで対象となる教育資金の一例を挙げると、主に、入園料や入学金、保育料、授業料のほか、通学バッグや教科書、制服など学用品の購入代金も対象となります。贈る側も受け取る側もよく考慮した上で利用しましょう。